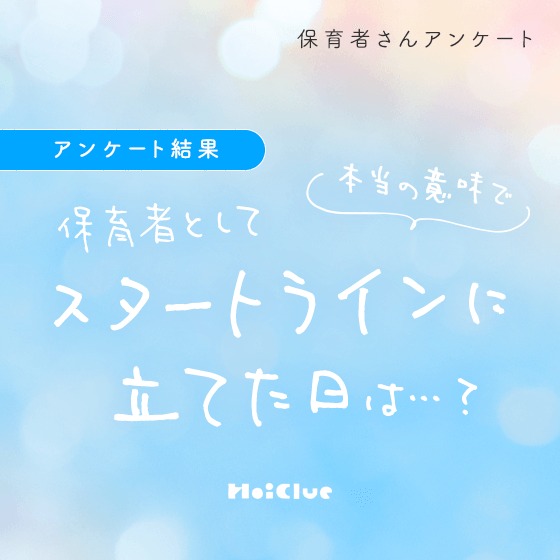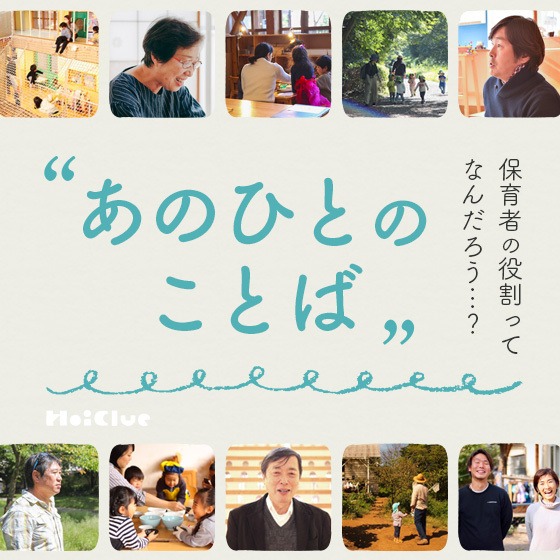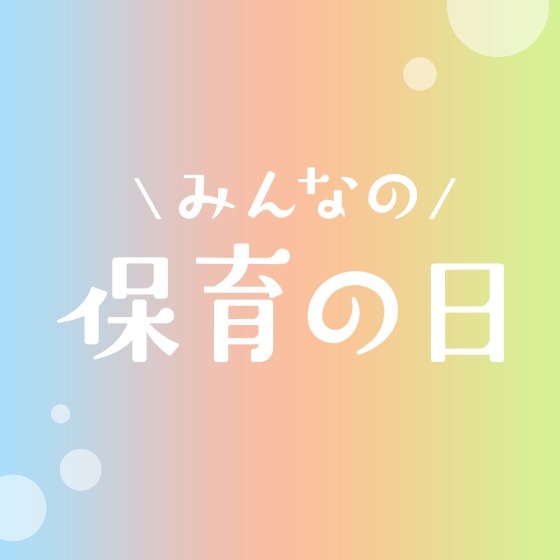みんなの保育の日とは?(4月19日)

でも一体、どんなことをする日なのでしょう…?
ということで、「みんなの保育の日」についてのあれこれと、改めてじっくり“保育”について向き合うきっかけになりそうな、読みもの記事をご紹介します。
みんなの保育の日(4月19日)
みんなの保育の日は、「保育」について改めて、社会全体で考えるきっかけを作ることを目的とした日です。
子育てや保育に関する様々な課題が浮き彫りになっている状況の中、保育者はもちろんのこと、保育者だけでなく、様々な視点や立場から、改めて「保育」というものについて共に考えたり、考えを共有したり向き合うきっかけにしたいという想いが込め、ほいくるを運営しているキッズカラーが2015年に記念日登録を行いました。
4月19日を4(ふぉー)19(いく)と読む語呂合わせから、4月19日が保育の日です。
みんなの保育の日ホームページ
みんなの保育の日について、詳しくはこちらをご覧ください。
▶みんなの保育の日ホームページはこちら
2025年のHoiClueでの保育の日プロジェクト
だいじなことは、子どもたちが気づかせてくれる。
子どもが夢中になっていることって、大人が見過ごしてしまっているようなことだったり…。
素直で無理のない言葉や行動で、私たちをハッとさせてくれることがあったり…。
保育の中で、子どもたちのちょっとした行動や言葉から、教わることがいろいろとあります。
皆さんも、そんな瞬間に出会ったことはありませんか?
4月19日の保育の日に寄せて、保育って…。子どもたちとの暮らしって…。と少し立ち止まって考えられるきっかけになればと思い、これまでHoiClueで取材をした方や園の記事を通じて見つけたいろいろな“子どもたちが気づかせてくれたこと”をご紹介します。
素直で無理のない言葉や行動で、私たちをハッとさせてくれることがあったり…。
保育の中で、子どもたちのちょっとした行動や言葉から、教わることがいろいろとあります。
皆さんも、そんな瞬間に出会ったことはありませんか?
4月19日の保育の日に寄せて、保育って…。子どもたちとの暮らしって…。と少し立ち止まって考えられるきっかけになればと思い、これまでHoiClueで取材をした方や園の記事を通じて見つけたいろいろな“子どもたちが気づかせてくれたこと”をご紹介します。
これまでの みんなの保育の日プロジェクト
ここからは、「みんなの保育の日」を通して、これまでに実施したプロジェクトをご紹介します。
今こそ、保育の現場と子どもに目を向ける〜ほいくるが考える「みんなの保育の日」〜(2017)
保育に関する様々な課題が浮き彫りになっているなかで、本当に大事なことってなんだろう。
保育士さんの本音、親の本音、答えのない保育のカタチ、子どもの姿…
「みんなの保育の日」をきっかけに、さまざまな視点から、改めて“保育”というものを見つめ直す記事を、連載してお届していきます。
保育士さんの本音、親の本音、答えのない保育のカタチ、子どもの姿…
「みんなの保育の日」をきっかけに、さまざまな視点から、改めて“保育”というものを見つめ直す記事を、連載してお届していきます。
“子どもは社会で育てよう!”みんなの保育の日(2017)
「子どもは社会で育てよう!」というコンセプトメッセージの元、保育に関係するさまざまな企業や団体で丸1日を通してイベントを開催しました!
「やらなきゃいけないこと」から「未来も踏まえて重要なこと」へ。 ー ほいくる生みの親・雨宮みなみが考える、いま保育に必要なこと。(2020)
4月19日は、4(ふぉー)19(いく)で、保育の日。
保育者はもちろんのこと、様々な視点や立場から「保育」というものについて共に考え、向き合うきっかけをつくりたいという想いを込め、ほいくるを運営しているキッズカラーが2015年に「みんなの保育の日」という記念日をつくりました。
そんな「みんなの保育の日」も今年(2020年)で6回目を迎えます。このタイミングに合わせ、何か新しい記事を読者のみなさんに届けることはできないか。ほいくる編集部で考え、普段一緒にほいくるのコンテンツをつくっているライター(三輪)が、ほいくる代表・雨宮に改めて「みんなの保育の日」を設立した想いやこれからの歩み、保育について話を聞くことにしました。
保育者はもちろんのこと、様々な視点や立場から「保育」というものについて共に考え、向き合うきっかけをつくりたいという想いを込め、ほいくるを運営しているキッズカラーが2015年に「みんなの保育の日」という記念日をつくりました。
そんな「みんなの保育の日」も今年(2020年)で6回目を迎えます。このタイミングに合わせ、何か新しい記事を読者のみなさんに届けることはできないか。ほいくる編集部で考え、普段一緒にほいくるのコンテンツをつくっているライター(三輪)が、ほいくる代表・雨宮に改めて「みんなの保育の日」を設立した想いやこれからの歩み、保育について話を聞くことにしました。
みんなの保育の日に寄せて、アドベントアンケート!(2021)
みんなの保育の日でもある4月19日に寄せて、ほいくるでは3月30日から20日間、Twitterにてアンケートを実施しました。
目の前の保育や、自分が思う保育とは異なる保育をしている人がいること、さまざまな考え方を知るなど、保育への視野を少し広げるきっかけになればと思っています。
目の前の保育や、自分が思う保育とは異なる保育をしている人がいること、さまざまな考え方を知るなど、保育への視野を少し広げるきっかけになればと思っています。
子どもが育つ社会について考える〜みんなの保育の日に寄せて 2022年ほいくる企画 〜(2022)
4月19日は、みんなの保育の日。
保育者はもちろんのこと、様々な視点や立場から「保育」について共に考えよう、という日です。
今年HoiClue(ほいくる)では、ほいくるサポーターさんといっしょに「これから、子どもにとってどんな社会になってほしいか?」「そのために、保育者として自分ができることは…?」という点について考えてみました。
保育者はもちろんのこと、様々な視点や立場から「保育」について共に考えよう、という日です。
今年HoiClue(ほいくる)では、ほいくるサポーターさんといっしょに「これから、子どもにとってどんな社会になってほしいか?」「そのために、保育者として自分ができることは…?」という点について考えてみました。
【アンケート結果】保育者として本当の意味でスタートラインに立てた日は…?〜保育の日に寄せて。保育者さんアンケート〜(2023)
心に残っている、保育者としての原点や出発点ともいえるようなできごとはありますか?
例えば、子どもに言われてハッとした経験や、先輩の保育者から言われたひと言の意味がようやくわかった…!といったエピソードなど。
今回は4月19日【みんなの保育の日】に寄せて、色々な角度から「保育」を改めて考えてみようということで、アンケートに寄せられた保育者のみなさんの、“本当の意味でスタートラインに立てた日”のことをご紹介します。
例えば、子どもに言われてハッとした経験や、先輩の保育者から言われたひと言の意味がようやくわかった…!といったエピソードなど。
今回は4月19日【みんなの保育の日】に寄せて、色々な角度から「保育」を改めて考えてみようということで、アンケートに寄せられた保育者のみなさんの、“本当の意味でスタートラインに立てた日”のことをご紹介します。
あのひとのことば〜保育って、保育者の役割って、なんだろう…?〜(2023)
リトルプレス「こどもこなた」から生まれた企画、“あのひとのことば”。
これまでにHoiClue(ほいくる)でインタビューさせていただいた方たちの、珠玉の“ことば”をご紹介する企画です。
今回はみんなの保育の日に寄せて、「保育って、保育者の役割って、なんだろう…?」という保育の原点にも触れる問いに重なる言葉を、集めてみました。
これまでにHoiClue(ほいくる)でインタビューさせていただいた方たちの、珠玉の“ことば”をご紹介する企画です。
今回はみんなの保育の日に寄せて、「保育って、保育者の役割って、なんだろう…?」という保育の原点にも触れる問いに重なる言葉を、集めてみました。
HoiClue編集部が出会った、保育の“まなざし”(2024)
HoiClueで紹介している、インタビュー記事。
これまでの取材を通して、すてきな園や子どもに関わるお仕事の方々にたくさん出会い、記事が生まれてきました。
4月19日の保育の日に寄せて…
HoiClue編集部が出会った保育の“まなざし”を、今回は過去3年間の取材記事の中から、ほんの少しだけ摘みとらせていただき、ご紹介します。
これまでの取材を通して、すてきな園や子どもに関わるお仕事の方々にたくさん出会い、記事が生まれてきました。
4月19日の保育の日に寄せて…
HoiClue編集部が出会った保育の“まなざし”を、今回は過去3年間の取材記事の中から、ほんの少しだけ摘みとらせていただき、ご紹介します。
保育について、改めて向き合うきっかけに
日々、目の前の子どもたちとの関わりや優先されるなかで、そもそも「保育」ってなんだろう…?と向き合う機会は少ないもの。
でも、だからこそ、時にはちょっと立ち止まって考えてみたり、振り返ってみたり、向き合う時間も大切かもしれません。
ここれでは、改めて今の自分の保育について向き合う機会になるような読みもの記事をご紹介します。
「子どもたちは、自分探しの旅をしている」— 汐見稔幸さんが考える本当の“保育の質”とは
2017年に「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」そして「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の3法令が改定され、いよいよ今年(2018年)4月に執行となりました。
この3法令の改定は、改めて保育者一人ひとりが、そして私たちほいくるが、自分たちの保育や子どもと向き合う姿勢、そして保育の質について考える機会でもあると思います。
そこで今回、改定にも大きく関わり、保育・幼児教育の第一人者でもある汐見稔幸さんにお話を伺うことにしました。
この3法令の改定は、改めて保育者一人ひとりが、そして私たちほいくるが、自分たちの保育や子どもと向き合う姿勢、そして保育の質について考える機会でもあると思います。
そこで今回、改定にも大きく関わり、保育・幼児教育の第一人者でもある汐見稔幸さんにお話を伺うことにしました。
大豆生田先生と考える。日本の「保育の質」ってなんだろう?
共著書「日本が誇る! ていねいな保育 - 0・1・2歳児クラスの現場から-」(2019年7月発行)を小学館より出版された、玉川大学教育学部・教授の大豆生田啓友先生。
大豆生田先生がここで述べている“ていねい”とは、“保育の質” とは何なのか。
じっくりお話を伺いました。
大豆生田先生がここで述べている“ていねい”とは、“保育の質” とは何なのか。
じっくりお話を伺いました。
一緒に見られている記事