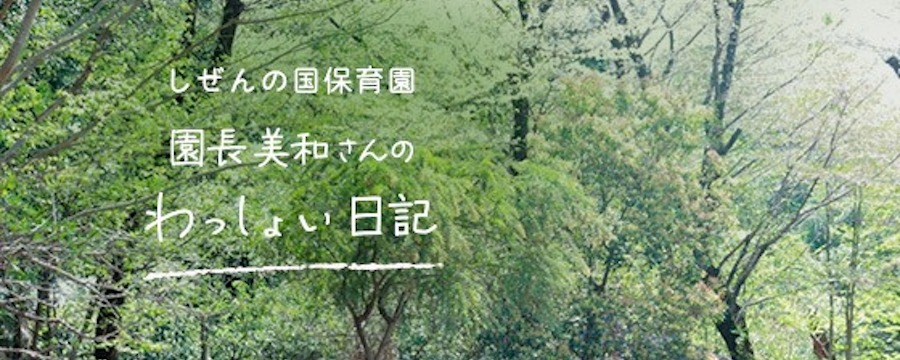「食べること、それを作ること、遊ぶこと。そこだけは外注しちゃいけない」:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.1(前編)

この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。
そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。
海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。
生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。
どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

連載をどうはじめるか考えたとき、真っ先に浮かんだのは、うみのこを運営する一般社団法人そっかの共同代表でもあり、日本スローフード協会理事、エディブル・スクールヤード・ジャパンのアンバサダーも務める小野寺 愛(おのでら あい)さんに話を聞くこと。
食べるってなんだろう。
幸せな食卓ってどうやったらつくれるのだろう。
食と子どもの関係をどう考えたらいいのだろう。
いろんな問いを持ちながらじっくりと話した愛さんへのインタビューから、「うみのこのとって食ってつながる暮らし」をスタートします。
小野寺愛 さん
一般社団法人そっか共同代表。日本スローフード協会理事、エディブルスクールヤード・ジャパンのアンバサダー。NGOピースボートに16年間勤務し、世界中を旅する中で「グローバルな課題の答えはローカルにある」と気づき、神奈川県逗子市にて海と森を園庭とする保育園「うみのこ」や小学生放課後の「黒門とびうおクラブ」の運営に情熱を注ぐようになる。子ども・自然・食をテーマとする講演、執筆、通訳・翻訳もライフワークで、翻訳本に『スローフード宣言~食べることは生きること』(海士の風)、『ランニングワイルド~世界至極のトレイル16章』(青土社)など。2024年には映画『食べることは生きること~アリス・ウォータースのおいしい革命』をプロデュース。趣味はカヌー、畑、おせっかい。三児の母。
三輪ひかり(聞き手)
うみのこの保育士。
保育士をしながら、執筆・編集の仕事もしています。
大きな問題に対しての答えを生きる人たちに会いに行く
ー 愛さんと食べることのはじまりはなんだったのか。そこからお話を伺えますか?
20代の頃、地球一周の船旅をコーディネートするピースボートで働いていました。そこで初めて紛争地に友だちができて戦争が人ごとではなくなったし、地球温暖化の影響で海辺に住んでいた人が移住しなきゃいけないような南太平洋の島に行って気候危機も自分ごととして捉えるようになりました。
最初はそんな現実を目の前に、環境破壊の現場や紛争地についてみんなにも知らせなきゃみたいな使命感で、そういう地域を訪れるスタディーツアーをいっぱい作っていました。でも自分に子どもが生まれて、子どもも一緒にピースボートで旅をするようになったら、“問題の現場”じゃなくて、その“大きな問題に対しての答えを生きる人たち”に会いに行きたくなったんです。

小野寺愛さん
そしてそこで出会ったのが、例えばイタリアで始まったスローフード(*1)だったり、アメリカのカリフォルニアで荒れた中学校を立て直すために始まったエディブルスクールヤードだったり。出会って「これは答えだ」と心から感動した活動が、たまたま食べることが切り口のものが多かったんです。
中でもエディブルスクールヤードが面白くて、人生を変えられた出会いでした。エディブルスクールヤードは、直訳すると「食べられる校庭」。全米で大人気のレストラン「シェ・パニース」のオーナーシェフ、アリス・ウォータースが始めた活動で、近所の荒れた公立中学校が気になっていたアリスが、「ここの子どもたちが自分たちで土から育てた新鮮な野菜を食べたら、子どもも学校も変わるんじゃないか」と思いついたことがはじまりでした。
まずは1エーカーあった教職員用の駐車場のコンクリートを剥がして、2年かけて畑を作ったのだけど、面白いのは、この畑(やキッチン)で食育をするだけじゃなくて、教科学習を行えるようカリキュラムを組んだこと!子どもたちが教室の外で、「おいしいね」と言いながら国語、算数、理科、社会を学べるなんて、あまりに画期的じゃないですか?
私が訪れた時は、タトゥーが入ってジャラジャラのネックレスをつけたヤンチャな中学生たちも、「世界一新鮮なサラダを食べさせてやるよ!」ってぱーっと畑まで走って、自分たちが育てたレタスを摘んで、自家製ドレッシングをかけて食べさせてくれました。その美味しさと、誇らしげな表情、生き生きと学ぶ姿が、本当に美しかった。
畑やキッチンで手を動かしながら学ぶ「エディブル教育」、創設から30年たった今では世界6000校以上に広がっています。日本中の学校もこうだったらいいのにと心に刻まれていて、うみのこを皆で立ち上げたときにも、食べることには絶対に大事に向き合いたいと思いました。
*1 スローフードとは:
食とそれを取り巻くシステムをより良いものにするための世界的な草の根運動。郷土に根付いた農産物や文化を失うことを始め、ファストライフ・ファストフードの台頭、食への関心の薄れを憂い、1989年にイタリアで始まり、現在160カ国以上に広まった国際組織でもある。「おいしい、きれい、ただしい(Good,Clean,Fairな)食べ物をすべての人が享受できるように」をスローガンに、食を真ん中に置いた様々なプロジェクトを行っています。
参考:[一般社団法人 日本スローフード協会]より。

うみのこの畑で採れたスナップエンドウ。生で食べても甘くておいしい。
私たちは食べたものでできている
ー 荒れた中学校を変革するほどの力が食べることにはあるんだと話を聞きながら感じたのですが、人間にとって「食べる」とはどんな行為なのでしょう?
大前提として、食べずに生きることができる人はいない。計算してみたら、1歳で食べ始めるとすれば、1歳から80歳までの間、ラッキーなことに1日3回食べられる人たちは人生で8万食も食べているんです。1食500円だったとして、誰もが4000万円も自分の食に投資しているということ。
私が翻訳したアリスの本『スローフード宣言〜食べることは生きること』の英語タイトルは『WE ARE WHAT EAT』。直訳すると“私たちは食べたものでできている”。本当にその通りで、人が食べることを通して自分の中に取り込んでいるのは、栄養価だけじゃない。価値観や文化も取り込んで、それが自分をカタチづくっている。食べるって、そういうことだと思うんです。
ー 食べることがその人の価値観や文化もつくる。
たとえば、忙しいからコンビニでサンドイッチを買って車の中で食べながら出発…というのは便利だから助かる時ももちろんある。でも、1日1食でも、里山を再生しようと頑張っている農家さんが育ててくれたお野菜を買って、その風景を想像しながら料理して、大好きな人たちと一緒に食べることができたら?少なくとも私はものすごく満たされて、ゴキゲンな1日を過ごせます。さらに、おいしい一皿の先で、微力ながら里山再生に参加することができると思うと、それもたまらない!
どこで誰がどんな風にして作ってくれた食材なのか、子どもたちにも伝えたいなと思います。知ることで何倍にも美味しくなるし、心も満たされるから。

うみのこの美味しいごはんをつくる、うみのこ食堂のスタッフ。スタッフは皆、地域のお母さんたち。
2年かけて翻訳したこの本(『スローフード宣言-食べることは生きること-』)でも、アリス自身が「ファストフードとスローフードは、食べ物だけの話ではありません。人は皆、食べることと同時にその価値観、文化も取り込んでいるのです」と言っていて。じゃあ、「ファストフード文化」ってたとえば何かというと、こう書いています。
- 便利であること
- いつでも同じ
- あるのがあたりまえ
- 広告への信頼
- 安さが一番
- 多いほどいい
- スピード
もちろん、これが全部削がれちゃったら大変です。こういうもののおかげで私たちの生活が豊かになったのは間違いない。でも、ファストに偏りすぎて失われるものがあるんじゃないかと問いかけているんですね。
一方で、1日1食でも、少しずつでも、特に子どもたちと共有したい「スローフード文化」としてあげているのが、たとえばこういうこと。
- 美しさ
- 生物多様性
- 季節を感じること
- 預かる責任
- 働く喜び
- シンプルであること
- 生かしあうつながり
私はピースボート時代、大人向けに平和教育、環境教育のプログラムを作っていたんです。でも、母親になってからは、もう起こってしまった環境破壊や紛争のことなどを大人に伝えるよりも、スローフード文化的な環境で子どもが育つ方が力強い社会変革になるんじゃないかと思うようになりました。一度、健全な循環とその心地よさを知った子どもたちは、大きくなった時にそれが削がれていることがあれば必ず気付いて、自ずと動く人になってくれるんじゃないかって。
だから、うみのこたちが逗子の海と山が大好きになってくれるのは、それだけですごいこと。たとえば、彼らが大人になった時に海で新しい開発が始まるとなったら、大好きな海を守りたいという想いから「何か違う方法はないかな」って自分で考えて動く人にきっとなる。誰かから机上で教えられて「課題解決をせねばならない」のとでは、モチベーションが全然違うはずなんです。
そんなわけで、実は小さな子どもたちとスローフード文化があたりまえという中で時間を過ごすことが、巡り巡って一番の世作りなんじゃないかと思っています。

この季節になると海岸にワカメが。うみのこの子どもたちも海に行っては拾い、茹でたり干したりして春の味をいただく。
出会うことと、命の大事な根っこ。
心地よさとか、本物のおいしさって、1回知ってしまったら一生モノとして子どもの中に残ります。
うみのこの子どもたちは、年に4回、SHO Farm(「千年続く農業」を掲げ、環境再生型農業といわれる「不耕起栽培」に挑戦する横須賀にある農園)に遠足に行きます。そこにいるだけで生き物の力を感じるような農園で、年長さんたちは種まきから三浦大根を育てさせてもらっているのだけど、SHO Farmの三浦大根は、切った瞬間に「じゅわっ」て水分が吹き出す気がするくらい、みずみずしくて甘い。あれを食べたら理屈抜きで自然と、「晶子さん(SHO Farm代表)のところの大根が食べたい!」となっちゃいます。
我が家も冬はずっとSHO Farmの三浦大根を食べているのだけど、この前、小学生の末っ子が地元の神社の行事で普通の大根をもらって帰ってきたんですね。「おお、でかした!じゃあ今日は豚汁作ろうね」と、大根を一緒に切って食べていたら、彼が「あれ。ママ、この大根、味がしないね」と言うんです。もちろん、まずいというわけでは決してなくて、ありがたくいただいたのだけど・・・美味しさを身体で「知っている」ってすごいな、豊かだなって改めて思いました。

SHO Farmにて種植えから行った三浦大根を収穫。
うみのこでSHO Farmに年に何度も遠足に行くのも、町のビストロのマスターと料理をつくり保護者を招待したレストランをするのも、養蜂家であるトシさんのはちみつの採取を毎年見学して食べさせてもらうのも、まずは出会うことが大切だから。
園庭で野菜を育てるのももちろんいいんだけれど、自分たちが普段食べているものを作ってくれている人や料理をしてくれている人を知らないって、命の大事な根っこがそがれちゃってる感じがして。
食べることも、それを作ること、そして遊ぶこと。そこだけは、外注しちゃいけない。子どもたちには、「ありがとう」に溢れる豊かなつながりの中で生きていてほしいなと思うんです。

***
撮影/執筆:三輪 ひかり
この記事の連載
「“とって食べる”の先に残るもの」子どもたちの心に根づく、手と感覚の記憶:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.1(後編)
うみのこを運営する一般社団法人そっかの共同代表であり、日本スローフード協会理事、エディブル・スクールヤード・ジャパンのアンバサダーも務める小野寺 愛(おのでら あい)さんへのインタビューから連載をスタートしました。
インタビュー前編で、「食べることも、それを作ること、そして遊ぶこと。そこだけは、外注しちゃいけない。子どもたちには、”ありがとう”に溢れる豊かなつながりの中で生きていてほしいなと思うんです。」と語った愛さん。
どんなふうに食べることや作ることを手元に持ち続けるのか。
後編では、一年を通してうみのこでどんな「食べること」にまつわる出来事が起きているのか、そこからお話をお聞きします。。
うみのこのとって食ってつながる暮らし
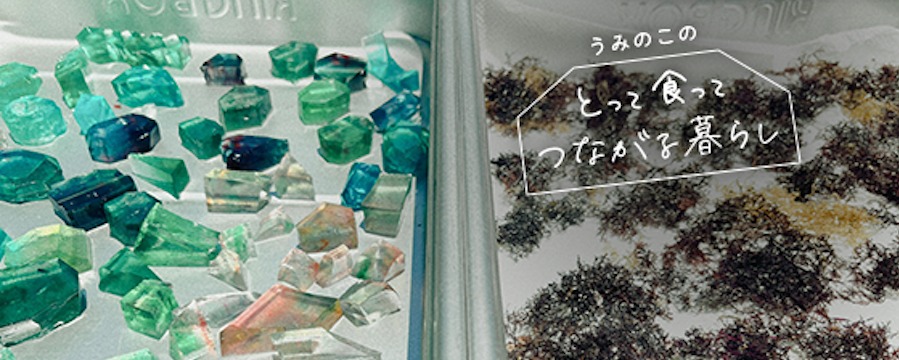
この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

からだに残る、育ちの時間:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.11
2026/02/13

関係がまざっていく、うどんづくり。うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.10
2026/01/16

「ごはんを食べながら、」特別編 :うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.8
2025/11/14

 うみのこ
うみのこ