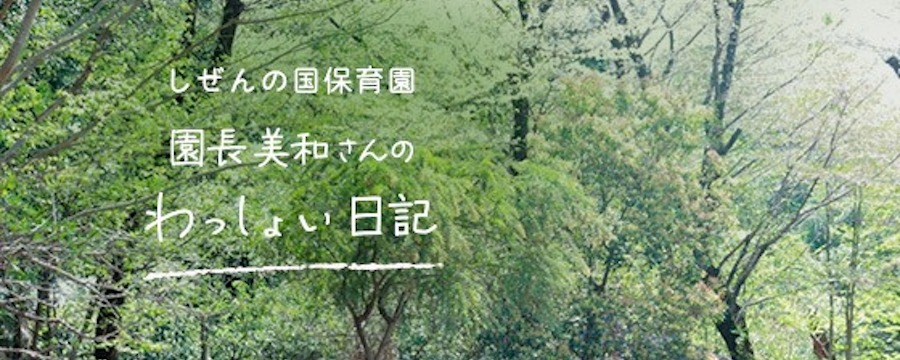「“とって食べる”の先に残るもの」子どもたちの心に根づく、手と感覚の記憶:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.1(後編)

新連載「うみのこのとって食ってつながる暮らし」。
うみのこを運営する一般社団法人そっかの共同代表でもあり、日本スローフード協会三浦半島支部理事、エディブル・スクールヤード・ジャパンのアンバサダーも務める小野寺 愛(おのでら あい)さんへのインタビューから連載をスタートしました。
インタビュー前編で、「食べることも、それを作ることも、そして遊ぶことも、そこだけは外注しちゃいけない。子どもたちには、「ありがとう」に溢れる豊かなつながりの中で生きていてほしいなと思うんです。」と語った愛さん。
どんなふうに食べることや作ることを手元に持ち続けるのか。
後編では、一年を通してうみのこでどんな「食べること」にまつわる出来事が起きているのか、そこからお話をお聞きします。
小野寺愛 さん
一般社団法人そっか共同代表。日本スローフード協会理事、エディブルスクールヤード・ジャパンのアンバサダー。NGOピースボートに16年間勤務し、世界中を旅する中で「グローバルな課題の答えはローカルにある」と気づき、神奈川県逗子市にて海と森を園庭とする保育園「うみのこ」や小学生放課後の「黒門とびうおクラブ」の運営に情熱を注ぐようになる。子ども・自然・食をテーマとする講演、執筆、通訳・翻訳もライフワークで、翻訳本に『スローフード宣言~食べることは生きること』(海士の風)、『ランニングワイルド~世界至極のトレイル16章』(青土社)など。2024年には映画『食べることは生きること~アリス・ウォータースのおいしい革命』をプロデュース。趣味はカヌー、畑、おせっかい。三児の母。
三輪ひかり(聞き手)
うみのこの保育士。
保育士をしながら、執筆・編集の仕事もしています。
うみのこ
神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしている。
うみのこの食べること、作ること。
うみのこたちは“食べる”ことに忙しいんです。
春は野草を摘んでは天ぷらでいただく。海では小さなスジエビやカニを網でつかまえて出汁をとったり、唐揚げにして給食前のお通しにしたり。夏になれば天草を拾って琥珀糖を作り、”ほうせきやさん”として振る舞ったり、秋はお芋掘りに枝豆の収穫、どんぐりクッキーも。冬になれば春に仕込んだ醤油を搾り、SHO Farmでは大きな三浦大根を収穫して、ルーから手作りの大根カレーをいただきます。3月、海でワカメ拾いがはじまれば、次の春はもうすぐそこだなと感じます。
.jpg)
捕まえたスジエビは海で焚き火をして、その場で食べることも

とある秋、デッキで枝豆の殻むき。翌年の醤油づくりのための大事な手仕事。

どんぐりホットケーキをつくったこともあります。
さわちゃん(食育担当スタッフ)がやってくれている食育がとにかく素晴らしいんです。内容ももちろんだけど、何の強要もしていないところがいい。日常の中で、お料理が大好きなさわちゃんが美味しいものを作っている。一緒に夢中になって最後までやる子もたくさんいるけれど、途中で飽きて飛び出す子もいて、それもOKという空間。
面白いことに、自分で作ること、作ったものを食べてもらうことってみんな大好きだから、飽きて途中で作ることをやめた子も、いい匂いがしてくる頃にはまた場に戻ってくるんですよね。海や山で遊んできた他のお友だちが帰ってくると、誇らしげに「僕が作ったんだよ!」なんて言ったりもして、子どもたちの喜びがひしひしと伝わってきます。

年長組のおもち&豚汁づくりがあった日。SHO Farmの畑に自分たちで種植えをした三浦大根で大根おろしを、苗植えをしたたのくろ豆できな粉をつくり、餅屋をオープン。みんなが育てたもので、みんなで料理をした給食は格別!
そんな風にたくさん作ってたくさん食べて、3年経つ頃には町のビストロのマスターもびっくりする包丁使いになる。年長組になると、集大成として保護者を招いて「うみのこレストラン」を開くんですが、昨年度の年長組は、パテはもちろん、バンズも手作りでハンバーガーを作りました。園庭で育てた大根のピクルスに、トウモロコシの芯から出汁を取ったコーンスープ、最後にはクレープまで出るフルコースを自分たちで作り上げていました。

お客さん一人ひとりに愛のこもったフラッグまでついていたりして、心もお腹も満たされました。子どもたちが相談して決めるので、メニューは毎年変わりますが、器から手作りをしてラーメン屋さんをした代もありましたよ。みんな本当にプロ顔負けの心のこもった料理とおもてなしをしてくれる。
どれも一日で成せるものではなくて、年間を通して日々の中に食べることや作ることがたくさん散りばめられているからこその姿だなと思っています。
とって、食べる。
ー 食べることや作ることを手元に持ち続けるために、まずできることってなんなのでしょうか?
まずは、近所で「とって食べる」を探すこと。
うみのこだったら、お散歩でとってきたヨモギや蕗を天ぷらにして食べたり、海に網を持っていって捕まえたスジエビをとれた子から順番に給食のお通しで食べるみたいなこと。園庭に畑がなくても、素晴らしい食育の先生がいなくても、「とって食べる」からなら始めやすいんじゃないかなって思います。

蕗の葉のてんぷら。揚げたてがおいしい!!
自分の暮らしている地域には野草がないと思う方もいるかもしれないけど、私、一度都内でエディブルスクールヤードのイベントをしたことがあるんです。大都会・青山でも「意地でも食べられるものを探してみせる!」と思って、参加者の皆さんと一緒に街を散歩して歩いたことがあるんです。そうしたら、街路樹のあしもとにヨモギも生えていたし、カラスノエンドウもあって。実は、探せばどこにでもとって食べられるものってあるんですよね。
生産者さんが立派な野菜を作ってくれたり、お父さんお母さんや給食の先生がおいしく料理をしてくれたものを食べるのは最高だけど、自分で摘んできたカラスノエンドウの若芽をソテーして食べてみたら「あ、おいしい!」みたいな経験って、肚落ち感がすごい。プリミティブなほど、直球で「嬉しい」んですね。子どもたちにはその感動が最初のステップとして、一番伝わるような気がしています。

小野寺愛さんとうみのこの子どもたち。この日は庭にいちごの苗を植え、野菜の種を蒔いた。
ー まさに、今回の連載企画のタイトルを「とって食ってつながる暮らし」としたのも、そこが原点だと思ったからでした。
この「つながる」というところで言うと、年少さんの時は、あるだけとりたいし、とれたら嬉しいし、食べたらおいしい、なんだけど、2回、3回と季節を巡る間に、子どもたちは自然のめぐりやつながりも覚えていくんですよね。
海でカニとりをしていると、年長児が「あ、そのカニはお腹が大きいからお母さんだ。離してあげよう」「お母さんカニは100個とか卵を持っているんだよ。離したら、数年後にもっとたくさんのカニに会えるかもしれないよ。」と年少児に声をかける姿がある。
森を歩いていると、春には野いちごに出会えますが「全部取っちゃったら、次の年には出てこなくなる。野いちごのつぶつぶ一つひとつが種だから、いくつか残しておこう。他の散歩の人も楽しみにしてるかもしれないしね。」というような学びもある。
それって、教室の中でどれだけ上手に教えてもらっても、実感としてはなかなかわからないことかもしれません。でも、小さな時からおいしさの実感とともに手を動かしながら「わかる」ことは、確実にその子の中に残るんだろうなと思うんです。

春になると出会える野いちご。甘い春のご馳走。
一皿が未来をつくる
ー 最後に、愛さんの考える、幸せで豊かな「食べること」はどういうものなのか教えていただけますか?
誰と食べるかはもちろん大事。加えて、どこで誰がどんなふうに育てた食材かも、とても大事です。目の前のひと皿の先に広がる自然も人も、皆がハッピーであることを知りながら、皆で料理をして、食卓を囲む。食べる人に美味しく、つくる人にやさしく、地球も元気になる — そんなふうに、つながりが全部分かるときに「ああ、幸せ!」と満たされます。
ちょうど週末、とても幸せなおいしい時間を過ごしました。私の20代の頃の恩師でもあった辻信一さん(文化人類学者、環境活動家)も関わって始まった、山口県にある自然農の学校「ゆっくり小学校」におじゃましてきたんです。そこには塩と油以外、調味料も全部、自家製でつくる畑と厨房がありました。そこで作ったものでランチを出すカフェもあって、私たちが訪れた日は定休日だったのにも関わらず、「ごはんは出せないんだけど、おはぎを作ったよ」と、皆さんで育てたお米、小豆、お砂糖でできたおはぎを出してくれたんです。
その日は雨だったけれど、風景は見渡す限り、桃源郷。遠くに見える森は杉だらけではなく、いろんな種類の広葉樹が広がっていて、目の前を流れる川の水もすごく綺麗。「ちょっと歩いたら水源だよ」などと教えてもらいながら、おいしいおはぎをいただきました。水源から里山までを見渡しながら、その土地と人の手が大事に育んだものをいただく。まさに、なんて幸せなんだろうと思いながら食べました。


幼児教育に関わっていると、「うちの子には安心安全な食を」という意識のある保護者が増えているのを感じます。でも実は、我が子のひと皿だけがオーガニックに変わったところで、我が子の未来を守れない。そのひと皿がどこから来ていて、それを作ってくれた農家さんは誰で、どんな農業や暮らしを営んでいて、そこにある風景はどうなっているか、というところまで皆で見ていけたらと思います。食べる人だけでなく、作る人も、生産してくれる土地や海も健全に循環していなかったら、元も子もないから。私は、毎日食べる一食をどこから調達して成り立たせるかで、子どものからだの安心安全だけじゃなく、子どもたちの未来全体、社会全体を安心安全なものに作りかえていくことができると考えているんです。
分断された食のシステムが変われば、社会はきっと変わる — そんな直接的な言い方で信条を押し付けたりはしませんが、「楽しそうだからやってみたい」「こっちのほうが確かに心地いい」と感じてもらえるといいなと思います。ファストフード文化にノーと言うのではなく、スローフードに魅了していくことで、ね。
- ファーストフードとスローフード

だって、野菜が嫌いって言っていた子が園庭の畑でとったピーマンなら生で食べるんですよ。登園したらデッキで皆がナスを塩もみしていたから、思わずパクリ、とか。キンカンも皆おいしそうに、木に手を伸ばしてはとって食べるを繰り返す。酸っぱいんじゃないかなと思いますけどね。スローフード(文化)は、面白いし、幸せそうだしで、やりたくなっちゃうんですね。
なんかあれよかったな、心地よかったな、またやりたいな、と感じられる場づくりが大事。それが広がれば、この地球の、子どもたちの未来は自ずと変わっていくんじゃないかなと、本気で思っています。

ある日の給食:前年度の年長組が仕込んでくれた八重桜の塩漬けを混ぜ込んだ子どもたちの手作りうどん、庭のヨモギとたんぽぽの天ぷら、逗子海岸でとったわかめのサラダ。WE ARE WHAT EAT!
***
撮影/執筆:三輪 ひかり
この記事の連載
「食べること、それを作ること、遊ぶこと。そこだけは外注しちゃいけない」:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.1(前編)
この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。
そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。
海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。
生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。
どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。
うみのこのとって食ってつながる暮らし
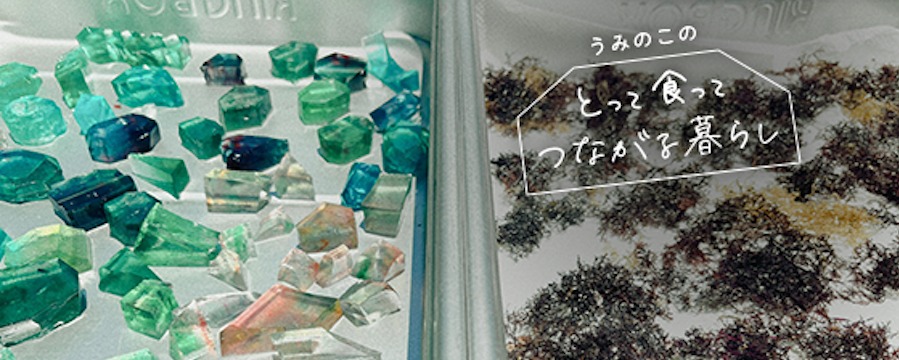
この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

からだに残る、育ちの時間:うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.11
2026/02/13

関係がまざっていく、うどんづくり。うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.10
2026/01/16

「ごはんを食べながら、」特別編 :うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.8
2025/11/14

 うみのこ
うみのこ