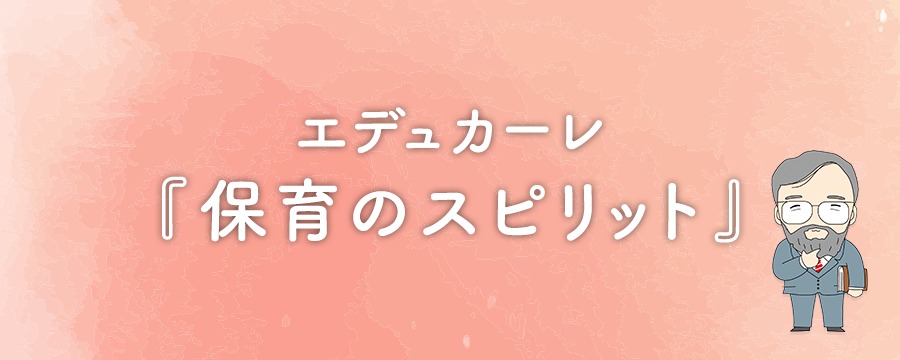春のご馳走。いただきます、食べられる野草! :うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.3

この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。
そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。
海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。
生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。
どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。
大人のおいしい遠足
うみのこでは毎年新年度がはじまると、保護者向けに緊急時の避難経路でもある近くのトレイルを歩きながら食べられる野草を探す、「大人のおいしい遠足」を開いています。

和ハーブフィールドマスターの資格がある、野草に詳しいスタッフのまきちゃんがガイドをします。
なんでもなかった道が、食べられる野草を知るだけで特別な道に見えてくる。
一度覚えると「あそこにもあった!」「ここにもある!」と、身近にこんなにたくさんの食べられる野草があったことに驚きます。
はじめの一歩は、植物に詳しい人と一緒に歩いたり、図鑑を片手に歩いてみること。その積み重ねで、うみのこの子どもたちも大人たちも、あっという間に身近な植物について詳しくなっていきます。
うみのこではこの機会だけでなく、普段子どもたちが遊んでいるフィールドに保護者のみなさんを誘ったり、保育に参加してもらえる機会を一年を通してたくさん用意しています。逗子の海山で過ごす心地よさや、おいしいものを食べる喜びを、子どもだけでなく、大人にも感じてもらいたいという願いからです。
この日も、少し進むと立ち止まる、まるで子どものように道草しながら歩く大人の姿があちらこちらにありました。

*自然の恵みをいただくときに忘れずにいたいこと
- 自分たち以外にも採取することや観賞することを楽しみにしている方がいらっしゃるはずなので、ほんの少しだけおすそ分けいただくつもりで採りすぎない。
- 口にするのは、食べられると確信できるものだけ。毒がある植物もあるので、分からないものは絶対に食べない。
- 場所によっては犬のお散歩コースの場合も。洗ってから食べるようにする。
- 他人の所有している畑や庭などには立ち入らないように注意する。
- 春の野草は、苦みやアクなど多量に摂ると身体によくない成分を含むものもあるので、食べ過ぎないように注意する。
当日教えてもらった野草の紹介
◯サルトリイバラ
分類:サルトリイバラ科 シオデ属
柔らかい若芽や若葉は、天ぷらにして食べられます。
猿もトゲに捕まってしまうという由来から「猿捕茨(サルトリイバラ)」と呼ばれているように、茎にトゲがあるから採るときは注意が必要。
西日本では、柏餅を包むのに柏の葉の代わりに使われることもあり、うみのこでも、サルトリイバラの葉を使って柏餅を作っています。
◯イタドリ
分類:タデ科 ソバカズラ属
水分が多い野草で、独特の酸味があります。昔は伸びてきたばかりの若い中空の茎を折って、お腹がすいたり、喉が乾いたときに、おやつがわりにかじって食べていたのだそう。
若芽や若葉は天ぷらにして食べられます。
茎は湯がいてアク抜きをして、きんぴらやジャムにしても◎
◯八重桜
分類:バラ科 サクラ亜属
八重桜はいろんな楽しみ方ができます。
花や若葉を塩漬けにして、桜餅やおむすび、うどんなどの料理に使ったり、蕾で甘いシロップを作ったり。花は天ぷらにすると、見た目も華やかでおすすめ。
うみのこでも年中組の子どもたちが、自分たちで摘んで塩漬けした花と葉を使って桜餅をつくり、保護者向けに「桜餅や」を開店していました。
売り上げは、年中組みんながやってみたい食育に活用していく予定です。

子どもたちのつくった桜餅。香りもおいしい春の味。
◯たんぽぽ
分類:キク科 タンポポ属
日本在来のカントウタンポポやシロバナタンポポでも、ヨーロッパからやってきたセイヨウタンポポでも、どちらも花や若葉を天ぷらにして食べられます。花は揚げるとほっくり甘みがあっておいしく、葉は独特な苦味が特徴的。
若葉は生のまま、サラダにして食べることができます。葉や茎はアク抜きをして、おひたしや和え物でいただくのも◎
◯ヨモギ
分類:キク科 ヨモギ属
一度見分ける方法を知ると、すぐヨモギとわかることができる特徴がある野草。
ヨモギの一つめの特徴は、葉の表側は緑色ですが、裏側は綿毛が密集して白色をしていること。採る前に葉の裏側を必ず見てみてください。もう一つの特徴は、手で揉むと独特の香りが漂うことです。
若芽や若葉は天ぷらで食べられます。葉をゆでて刻んですり鉢ですり、団子の粉と混ぜて茹でてよもぎ団子にするのもおすすめ。
葉を揉んだ汁は虫刺されのかゆみ止めにもなります。うみのこの子どもたちは、散歩中に蚊に刺されるとヨモギを探し、自分で揉んでかゆいところに塗っています。
◯みつば
分類:セリ科 ミツバ属
3枚の葉が、中央でしっかりとくっついているのがミツバの葉の特徴。ヨモギ同様、独特な香りがするので摘むときに香りも確認してみてください。
天ぷらやおひたし、サラダなどいろいろな料理で楽しめます。
◯カキドオシ
分類:シソ科 カキドオシ属
丸い扇形の葉が可愛らしいカキドオシ。4〜5月に淡い紫色の小さな花を咲かせます。
葉を摘んでみると、ミントやバジルのような爽やかな香りがするので、お茶にして飲んだり、生のままサラダや生春巻きなどに入れるのがおすすめ。天ぷらも美味しい。
***

摘んだ野草は洗って、種類ごとにわけると綺麗。

この日は天ぷらにして美味しくいただきました!
監修:
多田多恵子先生
(植物生態学者。「図鑑NEO花(小学館)」監修、ラジオ「子ども科学電話相談(NHK)」等に出演)
安藤麻紀子さん
(和ハーブフィールドマスター)
撮影/執筆:三輪 ひかり
※安全面の配慮に関して(小学館)
- 見分けが難しく危険な植物もあるため、あいまいなものは安易に食べないようにしましょう。
- 慣れていない場合などには、必ず植物に詳しい方と一緒に行くようにしましょう。
うみのこのとって食ってつながる暮らし
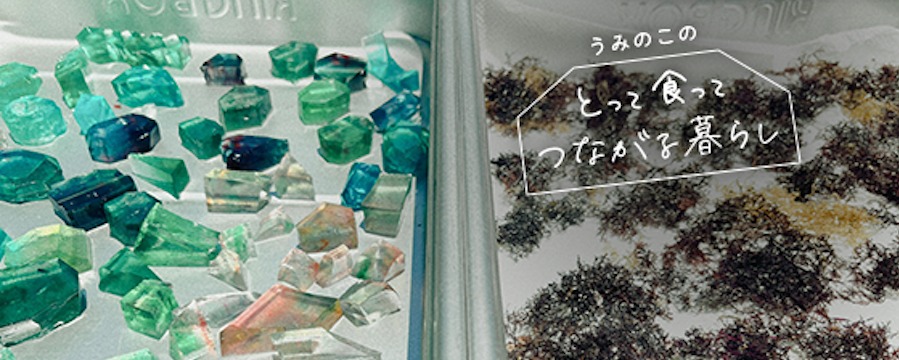
この連載の舞台になる「うみのこ」は、神奈川県逗子市にある認可外保育施設。逗子の山と海に囲まれた小さな古民家で、3歳〜6歳までの28人の子どもたちが暮らしています。そんなうみのこの暮らしに欠かせないのが、食べること。海山の恵みをいただき、畑で野菜を育て、自分たちで料理する。生産者、料理人、食べることに欠かせない人々とつながり、本物と出会う。どんなふうにうみのこで“食べる”ことが起きているのか、一年を通してお届けしていければと思っています。

関係がまざっていく、うどんづくり。うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.10
2026/01/16

「ごはんを食べながら、」特別編 :うみのこのとって食ってつながる暮らしVol.8
2025/11/14

 うみのこ
うみのこ