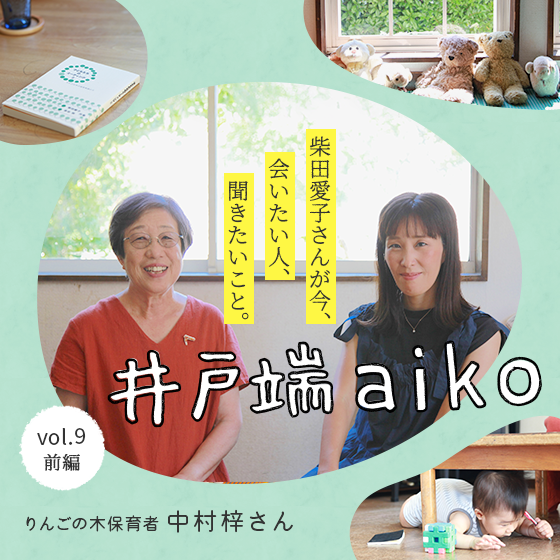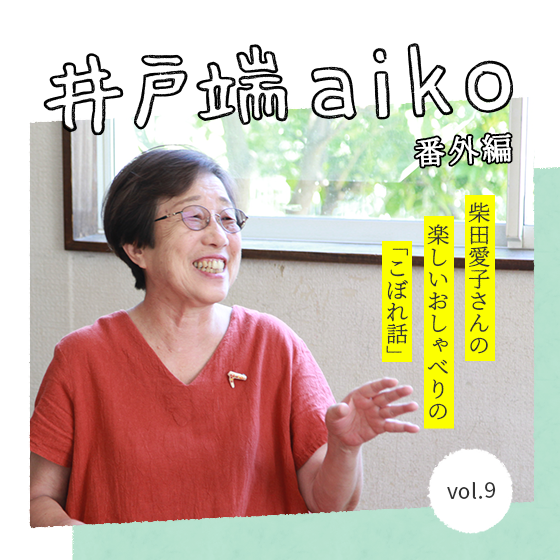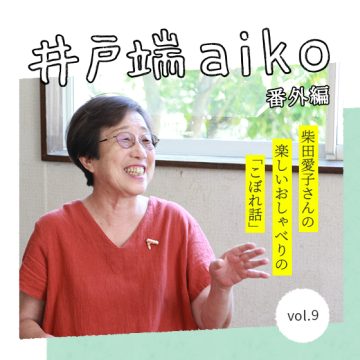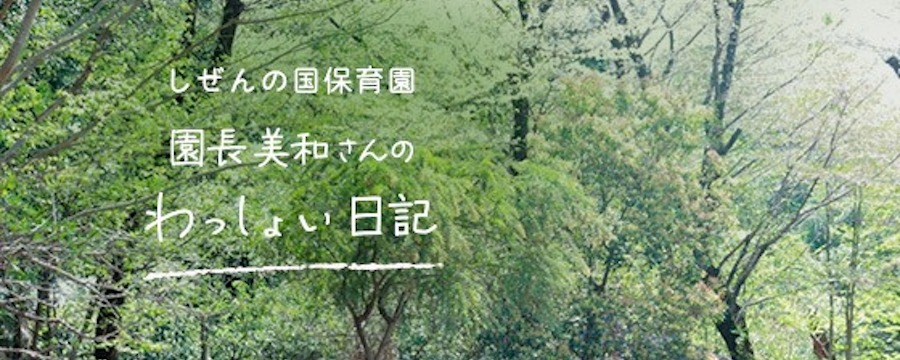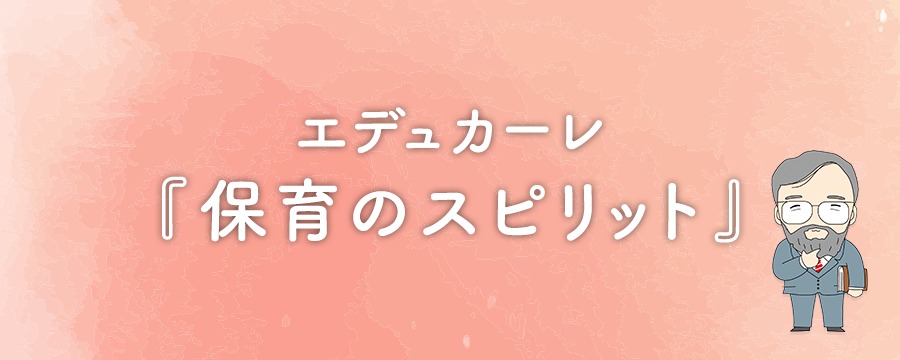「まわり道が育てるものがある。」_りんごの木子どもクラブ 柴田愛子さん×金谷梓さん〈後編〉

りんごの木子どもクラブの柴田愛子さんが、子どもの世界の淵(ふち)にいる方とおしゃべりをする連載「井戸端aiko」。第9回目のおしゃべりのお相手は、りんごの木子どもクラブの保育者である金谷梓さん。前編では、りんごの木で働くことや個が尊重されるということについてお話してくださいました。後編では、最近のりんごの木の保育についてたっぷりと語ってくれます!
金谷梓さん
1982年群馬県生まれ。
幼稚園、保育園で働いた後、お母さん業に専念。溺愛する息子の卒業と入れ替わりでりんごの木の保育者として働き始める。
ここ数年は、ミーティングの奥深さと面白さに魅せられて、奮闘中。
柴田との共著『子どもたちのミーティングⅡ -りんごの木の保育実践から-』
また、職場を越え、保育を語り合う場として、りんごの木の保育者長谷川と「ちいさいセミナー」を企画、運営。今年度もたくさんの方に参加していただいています。
柴田 愛子さん
1948年、東京生まれ。
私立幼稚園に5年勤務したが多様な教育方法に混乱して退職。OLを体験してみたが、子どもの魅力がすてられず再度別の私立幼稚園に5年勤務。
1982年、「子どもの心に添う」を基本姿勢とした「りんごの木」を発足。保育のかたわら、講演、執筆、絵本作りと様々な子どもの分野で活動中。テレビ、ラジオなどのメディアにも出演。
子どもたちが生み出すさまざまなドラマをおとなに伝えながら、‘子どもとおとなの気持ちのいい関係づくり’をめざしている。
著書
「子育てを楽しむ本」「親と子のいい関係」りんごの木、「こどものみかた」福音館、「それって保育の常識ですか?」鈴木出版、「今日からしつけをやめてみた」主婦の友社、「とことんあそんで でっかく育て」世界文化社、「保育のコミュ力」ひかりのくに、「あなたが自分らしく生きれば、子どもは幸せに育ちます」小学館、「それってホントに子どものため?」チャイルド本社、絵本「けんかのきもち」絵本大賞受賞、「わたしのくつ」ポプラ社、その他多数。
「こんな感じだよね」を抜け出したその先に。
愛子さん
りんごの木には、カリキュラムもないし、月案や週案といったようなものもないけれど、だんだん“りんごスタイル”みたいなものができてきて、保育が少しマンネリ化してきたように感じていたのよね。ワクワクした気持ちを保育者が持っていないというか、自分たちの知っている安全圏の中で子どもを動かすような感じになってきているんじゃないかって。
それで、何年か前の「とことん週間」(自分で決めた好きなことをとことんやり続ける一週間)の時には、「子どもじゃなくて、あなたはどこに行きたい?何したい?」って、保育者のみんなに聞いたのよ。保育者にも自分を掘り起こすというか、子どもと一緒に、これどうかな、あっちはなんだろうってワクワクしてほしかった。昨年は、「岡本太郎展に行く」っていうグループができて、すごく楽しそうだったわよね。

愛子さん
その経験を経て、今年度は大きい組は新しいことに動きを持っていってもらいたいという思いがありました。そこで長く4、5歳児を担任していた人に、子どもの原点である3歳児に入ってもらうことにしたの。もちろん、本人の意向も聞いてね。長く居るというのは、段取りもうまくなるし、どうしても他の人が頼ってしまう。安心、安全だからね。けど、新鮮なチャレンジやワクワク感が生まれにくくもなるのよね。私自身も気をつけたいと思うところ。
そして、この4月がスタートしたんですけどね、面白いよね。4月から、変わったのをすごく感じる。これからどうなってくかなって楽しみなのよ。
編集部
中にいる梓さんご自身も変化を感じていらっしゃいますか?
梓さん
そうですね。そして、その変化は「より面白い方向に」という、大人たちの意識がやっぱり関係している気がしています。
大人だけ先が見えすぎることをやるのも、子どもたちが大人の手のひらの上で転がされるのも、やめたいと思いながら日々過ごしてきました。そうしてわかったのは、大人も子どもも自分の力の全てを出しきらないと先に進めないぐらいの、ギリギリのところまでいかないと面白さには繋がらないということ。どちらも8割ぐらいの力で「こんな感じだよね」「毎日このくらいでいいよね」としてしまうと、新しい世界は開けないんですよね。
例えば、毎年、夏になると「ペガススの家」という施設に泊まりに行くんですけど、コロナ以降はバスで行っていたんです。でも、ここ数年当たり前になっていた日帰りペガスス(安心感を持って泊まれるように事前に日帰りでいく)や、「いってきます!」と言ってバスで出発し、ただ座っている間にもう到着している行き方に意味があるのかと、一度見直してみることにしたんです。そして、もう一度「自分たちの足でたどり着く」というのをやろうと決めました。

愛子さん
体験するということの中には、それにかかった時間や労力、体力、空間…と、いろんなことが詰まっているわけじゃない。でも今の世の中には、だんだんそのエッセンスだけを子どもに与えて体験させた“つもり”になっていることが、すごく多くなっているなぁと思う。
ペガススに泊まりに行くことをはじめた時は、電車を乗り継いで、最後2時間も歩いてようやく辿り着くというのをやっていて、そこにコロナがきて、今までやっていたことも見直すことになったんだけど「大変すぎたよね」っていう大人の声もあって、バスで行って泊まることになり、そこからさらに、「泊まりが不安な子も多いし、(バスで行けば)日帰りで行けるところにわざわざ泊まらなくてもいいんじゃない?」と、事前に日帰りで行ってから、一週間後に泊まりに行くスタイルになった。
私思うんだけどさ、便利さが奪い取っていくものってすごくあると思う。そういう気持ちを言ったか言わなかったか忘れてしまったけれど、今年のあずちゃんたちの姿を見て、伝わっていたんだなと思って嬉しかった。でも、そこに違う川にも行くっていう発想は私には全くなかったから、それも面白いなあと思ったわ!
梓さん
まずはいろんな川や渓谷に行ってみようと思って、電車に乗って川へ遊びに行くということを何度もしたんです。何度も何度も繰り返しやって、その先に「ペガススっていうところがあるんだけど行く?」と子どもたちに話してみることにしたの。
それまでに自分たちの足で行ったところはどこも楽しかったという経験をしているから、「きっと面白いことがある」という期待感が自分の手元にちゃんとあって、子どもたちの反応は今までのものと全然違った。
愛子さん
子どもたちの体がだんだんとできてくるのを感じられたのもよかったわよね。
梓さん
そうそう。電車で出かけていくということを繰り返す中で、自分の気持ちや体と向き合わなきゃいけなくなるんですよね。そうすると、自分の持てる荷物以外は持たないとか、そういうことがだんだん上手になってくる。
だからペガススへのお泊まりの時も、いつものリュックに入るものだけしか持っていかないように、自然になっていた。バスで行っていた時は、普段一緒に寝てないでしょと思うような巨大なぬいぐるみを持って行ったり、このために新しく買ってもらったような虫かごや網を持っていく子もいて、とにかくみんな荷物が多かったのに。
愛子さん
だから、宿の散らかりようが全然違ったわよね。前はこう、足の踏み場もないぐらいだったんだけど。

無駄に見えるものが子どもを育てる
愛子さん
だけどさ、大人の便利でありたい、安心安全でありたいという思いが、子どもをそうさせてしまったような気がするんだよね。
例えば、あずちゃんたちが渓谷へ行った時もね、こういうところよってスマホで行き先を事前に見せていた親がいて、「自分が安心するために見たいなら見てもいいけど、子どもに見せるのは、子どもの気持ちを奪い取ってしまう」と伝えたわ。
梓さん
そうやって何でも簡単にスマホやネットで見たり知ったりすることはできるけれど、それを見てから行くのと、見ずに行くのでは、最初の感覚が違うと思う。情報が多すぎると本当のその子の感覚とは違うものになっちゃうと思うんです。
愛子さん
大人のおせっかいが過ぎてしまいがちなのよね。
梓さん
でもだからこそ、保育の現場はそういう無駄だと思ってしまうようなこと、めんどくさくて、時間がかかるようなところを大事にしたいと思うな。ちゃんと子どもたちが自分の気持ちで考え、感じ、手を動かしたりして、自分の感覚を“私のものなんだ”って感じられる時間を積み重ねたいって思うんです。
愛子さん
スマホを無くすことはできないし、これからますます便利さが優先される時代になっていくと思うけれど、人間として進化した中でも譲れないもの、なくしちゃいけないものってあるのよね。なくなっては人が育たないものって絶対あると思うの。
梓さん
まわり道が本当は人を育てるよね。
ミーティングも特にそうな気がするんだけど、子どもの声を聞くって、効率から考えたらしないほうが楽だと思うの。だって、大人が言ったことを子どもに聞かせる、やらせる方が集団の扱いとしては絶対楽じゃない?でもそうしてしまったら、子どもの心は育たない。

梓さん
手間はかかるし、なかなか最初は子どもは喋らないし、喋ったと思ったらぐちゃぐちゃしてるし、違う話にいったりもするんだけど。それでも子どもの声を聞こうって、そうやって暮らしていこうっていうことは、捨てちゃいけないと思うんです。
愛子さん
そうね。子どもも大人も、一緒に考えて、しゃべって、楽しい日々を作っていきたいわよね。仲間として育っていく場なんですもの。
写真:雨宮 みなみ
写真提供:りんごの木子どもクラブ
この記事の連載
柴田愛子さんと金谷梓さんが語った、「りんごの木で働く」ということ。〈前編〉
第9回目のおしゃべりのお相手は、りんごの木子どもクラブの保育者である金谷梓さん。
14年ぶりに刊行された、りんごの木のミーティングについての本『子どもたちのミーティングⅡ -りんごの木の保育実践から-』にミーティングのエピソードを綴ったのが、梓さんです。
井戸端aikoでこれまで様々な方々とおしゃべりをしてきましたが、りんごの木のスタッフとはまだおしゃべりしてもらったことないなと思い、ほいくる編集部から「いかがですか?」とご提案をさせてもらって、梓さんとの対談が決まりました。
気持ちは“効率が悪い”――子どもたちの席決めから見えたこと。りんごの木子どもクラブ 柴田愛子さん×金谷梓さん〈番外編〉
第9回目のおしゃべりのお相手は、りんごの木子どもクラブの保育者である金谷梓さん。
盛り上がったおしゃべりの中で、泣く泣く本編からはカットした「愛子さんと金谷梓さんのこぼれ話」を、番外編としてお届けしたいと思います。
井戸端aiko

りんごの木子どもクラブの柴田愛子さんが、子どもの世界の淵(ふち)にいる方とおしゃべりをする企画「井戸端aiko」。いろいろな方をゲストにお迎えし、お届けしています。

 三輪ひかり
三輪ひかり