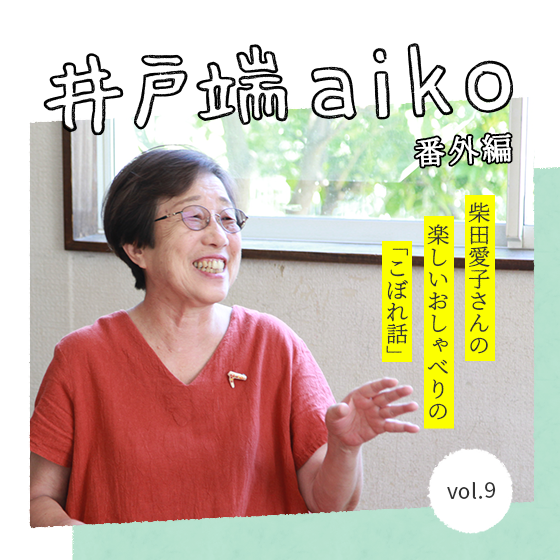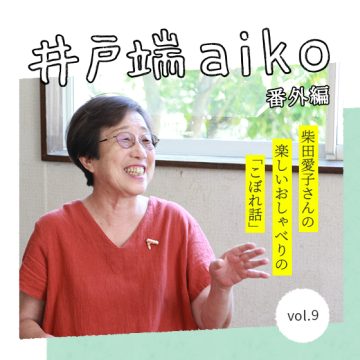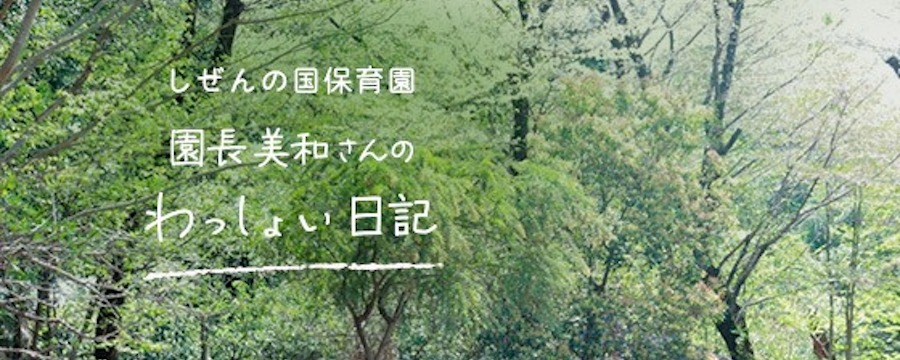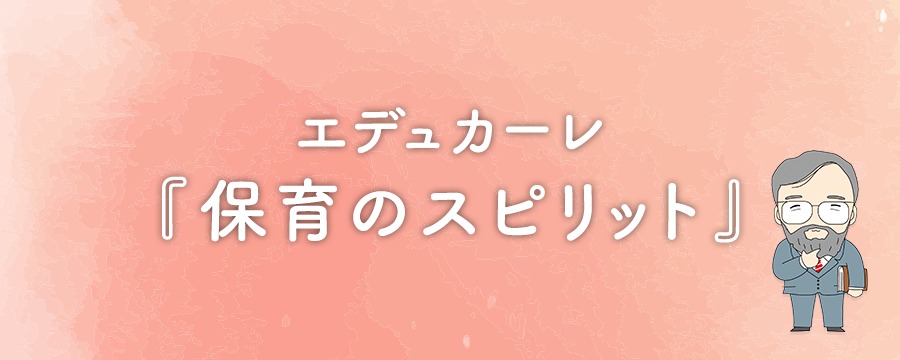柴田愛子さんと金谷梓さんが語った、「りんごの木で働く」ということ。〈前編〉

第9回目のおしゃべりのお相手は、りんごの木子どもクラブの保育者である金谷梓さん。
14年ぶりに刊行された、りんごの木のミーティングについての本『子どもたちのミーティングⅡ -りんごの木の保育実践から-』にミーティングのエピソードを綴ったのが、梓さんです。
井戸端aikoでこれまで様々な方々とおしゃべりをしてきましたが、りんごの木のスタッフとはまだおしゃべりしてもらったことないなと思い、ほいくる編集部から「いかがですか?」とご提案をさせてもらって、梓さんとの対談が決まりました。

りんごの木の保育者はなかなか個性的。それぞれの特徴を活かして、自分を、保育を、つくってほしいと思っています。あずちゃんは頭を整理し、文字にすることが上手だと思っています。その特徴を活かして、今回「ミーティングⅡ」の本を書いてもらいましたので、皆さんにもご紹介したいと思ったのです。
「井戸端aiko」おしゃべりのお相手は…
金谷梓さん
1982年群馬県生まれ。
幼稚園、保育園で働いた後、お母さん業に専念。溺愛する息子の卒業と入れ替わりでりんごの木の保育者として働き始める。
ここ数年は、ミーティングの奥深さと面白さに魅せられて、奮闘中。
柴田との共著『子どもたちのミーティングⅡ -りんごの木の保育実践から-』
また、職場を越え、保育を語り合う場として、りんごの木の保育者長谷川と「ちいさいセミナー」を企画、運営。今年度もたくさんの方に参加していただいています。
柴田 愛子さん
1948年、東京生まれ。
私立幼稚園に5年勤務したが多様な教育方法に混乱して退職。OLを体験してみたが、子どもの魅力がすてられず再度別の私立幼稚園に5年勤務。
1982年、「子どもの心に添う」を基本姿勢とした「りんごの木」を発足。保育のかたわら、講演、執筆、絵本作りと様々な子どもの分野で活動中。テレビ、ラジオなどのメディアにも出演。
子どもたちが生み出すさまざまなドラマをおとなに伝えながら、‘子どもとおとなの気持ちのいい関係づくり’をめざしている。
著書
「子育てを楽しむ本」「親と子のいい関係」りんごの木、「こどものみかた」福音館、「それって保育の常識ですか?」鈴木出版、「今日からしつけをやめてみた」主婦の友社、「とことんあそんで でっかく育て」世界文化社、「保育のコミュ力」ひかりのくに、「あなたが自分らしく生きれば、子どもは幸せに育ちます」小学館、「それってホントに子どものため?」チャイルド本社、絵本「けんかのきもち」絵本大賞受賞、「わたしのくつ」ポプラ社、その他多数。
保育者も一人ひとりを尊重したい
愛子さん
私ね、やっぱり子ども一人ひとりを尊重するのと同じように、保育者も一人ひとりを尊重したいと思うのよ。だから、りんごの木って働き方も普通の保育園とは全然違うの。
例えば、出勤時間が決まってない。「子どもより早く来てね」というだけで、「何時に来なさい」とは言わないの。それから、自分が休憩したいと思うタイミングって、他の人が測れるものじゃないでしょう。だから、「有給日数がどうとかよりも、自分で必要な時に休みたいと申し出てね」と言ってるの。あくまでも、りんごの木は自分スタイルの集合体にしたかったのよね。
保育も同じで、一般的にはカリキュラムがあって、今月の目標とかねらいを立てると思うんだけど、りんごの木にはそういうのが一切ない。これは、私自身が自分の思いで動くのが好きだからというのもあって。
あずちゃんは、他の幼稚園でも勤めたことがあるけれど、そういうりんごの木のスタイルに不安や働きづらさみたいなことはなかったの?
梓さん
私は、前勤めていた園で、カリキュラムがあるのが苦しいと思って保育をしていて。なるべく子どもに負担がかからない形でやれないかと工夫していたんです。だから、カリキュラムがなくて心地いいなと思っています。

愛子さん
それならよかった。でも、私びっくりしたんだけどさ、「こうしましょう」がないのに、あなたって勝手に目標を立てたり、保育日誌みたいな記録を書いていたりするじゃない。だから、自分で決められるならきちんとしたい人というか、企画したり、記録したりすることが得意な人なんだよね。
私は、保育や子どものことで覚えておきたいことっていうのは、全部映像で残っていくのよね。だから、文字になってないわけ、一切が。文字にするのが苦手というか、体から離れていく感じがするのよ。私はそういう人なのね。
梓さん
それ、すごいと思う。私は愛子さんのように映像記憶ができないけど、手がかりさえあればバッと記憶が蘇るの。だから、忘れたくないことを必ず記録しておきたいと思う人なんです。
編集部
梓さんのように記録をとることは、りんごの保育者の中ではめずらしいんですか?
愛子さん
あんまり聞かないね。私ほど、何もない人もいないけど(笑)。

愛子さん
保育者一人ひとりがどんな特徴を持っている人でそれがどう活きるのか、分かるまでに何年もかかることもあるけど、あずちゃんの場合は文章だと思った。それに気づいたのは、メールで一日の報告を送ってもらうことをしているんだけど、その時にあずちゃんが選んで使う言葉がとても素敵だなと思ったの。
だからね、『子どもたちのミーティングⅡ -りんごの木の保育実践から-』の本を出そうと考えたのは、あずちゃんの窓を本を一冊出すことで開きたいという思いもあってだったのよね。人を説得したり共感させたりすることを、保育の世界だけに閉じてしまうのではもったいない。その人が得たものを外に発信していくことも大事だと思うの。保育者が保育者を育てることに繋がるとも思うしね。
「私はこう考えます。あなたはどう考えますか?」
愛子さん
保育者にとっても、子どもにとっても、止まり木でありたい。飛んでいってもいいし、羽を休めに来てもいい。ずっと保育に浸っていたい人はいいんだよ、それで。保育の世界ひとつだって色々あるからね。でも、何かもう1つ世界を持ったらいいのになと感じる人には、今回のあずちゃんみたいにおせっかいを思うわけ。
最初はみんな自分のことがよく分からなかったり、自信がなかったりするけれど、やっていくうちに自信がつく。ケロポンズのポンちゃんがまさにそうだったのよ。りんごの木で保育をしていた頃は自信がなくて、「保育がつまらない」と言っていたの。
今でも覚えているのがね、保育がつまらないっていうのは子どもが見えていないということだから見えるようにしようと思って、保育者一人に7人の子どもという小さなグループで過ごせるようにしたの(編集部注釈:りんごの木の大きい組(4、5歳児)は通常、4、5歳混合で2クラスに分かれている)。それで、「あなたと子どもと好きなように過ごして」と言ったのよ。そうしたらね、ポンちゃんのグループどうしたと思う?毎日ケーキ屋さんに行ってたわよ。それで窓からお店の中を毎日見てたらね、そのうちお店の人がクッキーの切れ端をくれるようになったりして。
しばらくすると、「愛子さん、シュークリーム買ってもいいですか?」って言うからさ、「いくら?」「100円。」「じゃあ半分こだな」なんてやりとりをして、シュークリームを買いに行ったり。そんなことを1週間以上やっていたと思うんだけど、ポンちゃんも子どもも本当にイキイキしてた。だから、人を光らせるって、やっぱりその人が何を求めているかなのよね。やりたいことやってよくなったら、面白くなるのよ。

愛子さん
だけどさ、私は一人ひとりを尊重したいと思ってるけれど、実際働く人は、それぞれの個性が個性のままなわけじゃない。一緒に働くことの難しさみたいなものを感じる時もやっぱりある?
梓さん
難しさを感じる時もあるけれど、保育は順調に進んでるし、難しいと感じているのは自分だけかもなと思ったりするから、逆に愛子さんはどうしてきたのか聞きたいです。愛子さんも、周りに個性の強い人たちがいっぱいいる中で保育をしてきたわけじゃない?
愛子さん
私はやっぱり話してきた。例えば新沢くん(編集部注釈:シンガーソングライターの新沢としひこさん。以前、りんごの木で保育者をしていた)とも全然考え方やあり方が違うんだよね。それでね、3日ぐらいは自分で考えるんだよ。それから「話があります。どうしてこういうことをするんですか?」と聞いたらね、「え 何も考えてません。僕は自分がやりたかったらやるだけなんです。」って言って、何も変わらないのよ(笑)。
それでまた私が「これ気になるんだけどさ…」って話しかけての繰り返し。でも、その繰り返しの中であっちも嫌なことは言ってくるようになったりしてね。だから、話して折り合える時と折り合えない時があるし、もうその人とは折り合えないまま保育は進んでいくという時もあるわね。
梓さん
折り合いのつかないまま保育が進んでいくこともあるんだ。
愛子さん
そう、それはもうしょうがない。
編集部
でもそこで、「それはしないでください」「りんごの木ではやらないでください」とは言わないんですね。
愛子さん
だってその人の考えがあるんだもの。私にできるのは、「私はこう考えます。あなたはどう考えますか?」まで。それに、考えがないにしても、私はこう思いますっていう私の思いにその人が影響されないでいるっていうことは、もうそれがその人の色なわけじゃない。
「自由」ってなんだろう。
編集部
りんごの木の保育や、愛子さんのりんごの木の子どもと大人、両者への眼差しを見ていて、「個」を何より大事にしているけれど、その上で「個だけど群れ(集団)である」ということも絶対に軽んじないんだなということ感じました。
愛子さん
そうね。人間ってやっぱり群れで生きていく。群れて生きていて、その群れの中をよく見ると一人ひとりが違って、一人ひとりが違うから主体性や自由であるということがすごく育つし、光るんだと思うんです。
だって、自由が際限なく風船溜まりのようだったらその自由は手前勝手なただの我が快感だけになってしまうでしょう?だけどそこには他者がいて、不自由がある。不自由があるから、その中の自分の自由が光るんだし、いろんな人がいるからこそ、自分の主体性がはっきりと見えてくる。だから主体性を尊重するってことは、好き勝手を保障するということでは全然ないのよ。群れの中にいる仲間であって、だから違いを感じ、違いを尊重し合える関係になっていくんじゃないかしら。

梓さん
そこのバランスが変わると、ただの自分勝手な人の集合体になっちゃう可能性もある気がするんです。というのもね、りんごの木で何年か前に、子どもたちから「何をしてもいいでしょ、自由なんだから」って、まるで免罪符のように言われたことがあったの。その時私は、「あ、これはちょっとまずい方向にいってるな」って思ったんです。
自由だから自分の好き勝手でいいじゃんっていうのはやっぱり違うと思うんですよね。そこにいる仲間の気持ちだったり、快不快があって、一緒に暮らしているからこそ、その相手の思いを感じながら、自分自身で考えてほしいなと思う。
「自分はこうしたい。でもあの子がそう言うなら…」って折り合いをつけたり、「いや、でもそれでも僕は…」って譲れないと思ったり。そういう自由さを私たちはここで求めてるんだけれど、でもうっかりするとなんか言葉だけになっちゃう時があるんですよね。「自由なんだからいいでしょ」って子どもに言わせてしまう何かがその時のりんごにはあったということを、教えられた出来事でした。
写真:雨宮 みなみ
この記事の連載
「まわり道が育てるものがある。」_りんごの木子どもクラブ 柴田愛子さん×金谷梓さん〈後編〉
第9回目のおしゃべりのお相手は、りんごの木子どもクラブの保育者である金谷梓さん。
前編では、りんごの木で働くことや個が尊重されるということについてお話してくださいました。後編では、最近のりんごの木の保育についてたっぷりと語ってくれます!
気持ちは“効率が悪い”――子どもたちの席決めから見えたこと。りんごの木子どもクラブ 柴田愛子さん×金谷梓さん〈番外編〉
第9回目のおしゃべりのお相手は、りんごの木子どもクラブの保育者である金谷梓さん。
盛り上がったおしゃべりの中で、泣く泣く本編からはカットした「愛子さんと金谷梓さんのこぼれ話」を、番外編としてお届けしたいと思います。
井戸端aiko

りんごの木子どもクラブの柴田愛子さんが、子どもの世界の淵(ふち)にいる方とおしゃべりをする企画「井戸端aiko」。いろいろな方をゲストにお迎えし、お届けしています。

 三輪ひかり
三輪ひかり