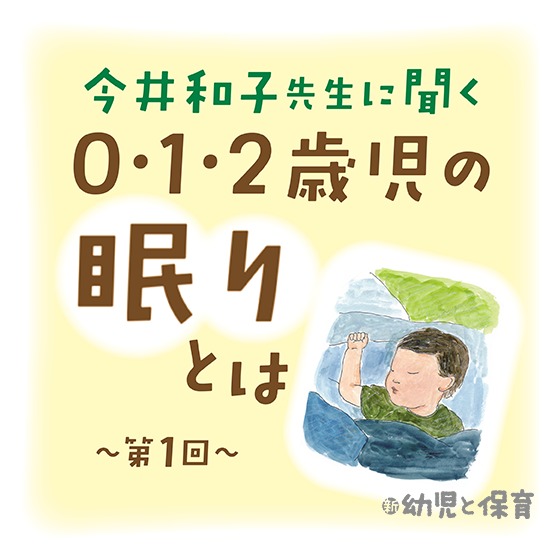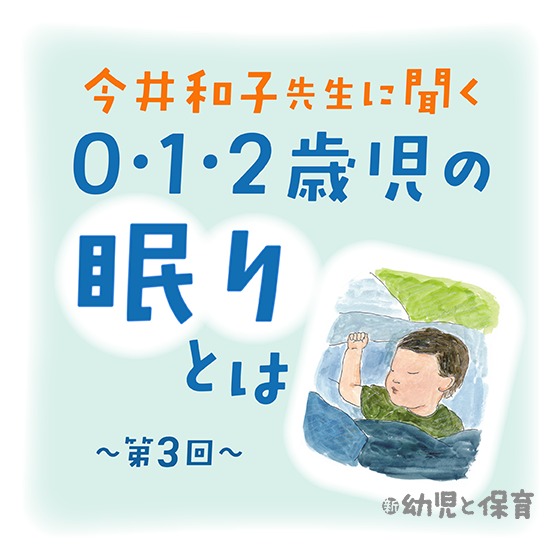今井和子先生に聞く 0・1・2歳児の眠りとは 〜第2回 睡眠リズムの変化と環境構成の工夫~

乳幼児にとって睡眠はなぜ重要なのでしょう。保育室で安心して眠れるようにするために、保育者が気をつけることは……?
乳幼児保育歴の長い今井和子先生に、ヒントを教わります。
第2回は「睡眠リズムの変化と環境構成の工夫」です。
(この記事は、『新 幼児と保育』増刊『0・1・2歳児の保育』2018春 に掲載されたものを元に再構成しました)
監修

今井和子先生
「子どもとことば研究会」代表。二十数年間公立保育園で保育者として勤務。その後、東京成徳大学教授、立教女学院短期大学教授などを歴任。現役保育者であったころからの経験をもとに、全国の保育研修なども行っている。著書に『0・1・2歳児の担任になったら読む本 育ちの理解と指導計画【改訂版】』、『0歳児から5歳児 行動の意味とその対応』(ともに小学館)など。
子どもにとって睡眠が重要なわけ
睡眠を中心にして、なぜ生活リズムを整えなければならないか。
「寝る子は育つ」というように、睡眠には、脳をつくり、育て、守り、よりよくするという働きがあります。大人の睡眠は身体や脳の機能を維持するためのものですが、乳児期の睡眠は身体や脳の機能をつくります。赤ちゃんは起きている間、五感をフルに働かせてさまざまな情報を得て、眠っている間にそれら情報を記憶として整理し、大脳を発達させているのです。
それに加え、生後3か月ごろから睡眠中に成長ホルモンが分泌されるようになります。
これにより、身体の新陳代謝を促し、細胞組織を修復し、再生します。そして、この時期の睡眠が、昼と夜の区別がつくようになる生活リズムをつくっていくためにも、重要だからなのです。
※月齢・年齢はあくまでも目安です。
新生児~2歳の睡眠リズムの特徴
新生児
1日あたりの睡眠時間が多い(1日の約3分の2)。
大人に比べてまどろみ(後のレム睡眠=浅い眠り)の割合が大きい。
生後2〜3か月
1日の半分以上眠って過ごす。
3〜6か月
睡眠時間は1日の約半分になる。生活リズムを身につける。
臨界期。朝決まった時間に起き、規則正しい授乳、昼間は起きて遊び、夜休むことを規則的にくり返す生活が重要。
6か月〜1歳
1日の睡眠時間は12〜13時間。
夜まとめて眠るようになる。脳の発達とともに、ノンレム睡眠(レム睡眠ではない深い眠り)が現れる基礎ができる。夜泣きが多くなる。
2歳〜
ノンレム睡眠とレム睡眠。
日中の運動量が増えるなどにともない、ノンレム睡眠が増え、夜の熟睡量が一生のうちで最も多くなる。
生活リズムの自立への第一歩
文/大石裕美 イラスト/奥まほみ
この記事の出典 『新 幼児と保育』について
保育園・幼稚園・認定こども園などの先生向けに、保育をより充実させるためのアイデアを提案する保育専門誌です。
▶公式ページはこちら
この記事の連載
今井和子先生に聞く 0・1・2歳児の眠りとは〜第1回 家庭での生活リズムを把握して子どもに合わせた環境をつくる〜
そんな環境の中で乳幼児が安心して眠れるようになるために、大切なことは何でしょう。
乳幼児保育歴の長い今井和子先生に、ヒントを教わります。
第1回は「家庭での生活リズムを把握して子どもに合わせた環境をつくる」です。
今井和子先生に聞く 0・1・2歳児の眠りとは〜第3回 安心して眠れるために気持ちを安定させる5つの心得〜
乳幼児保育歴の長い今井和子先生に聞きました。
シリーズ第3回は「安心して眠れるために気持ちを安定させる5つの心得」です。

 新 幼児と保育
新 幼児と保育