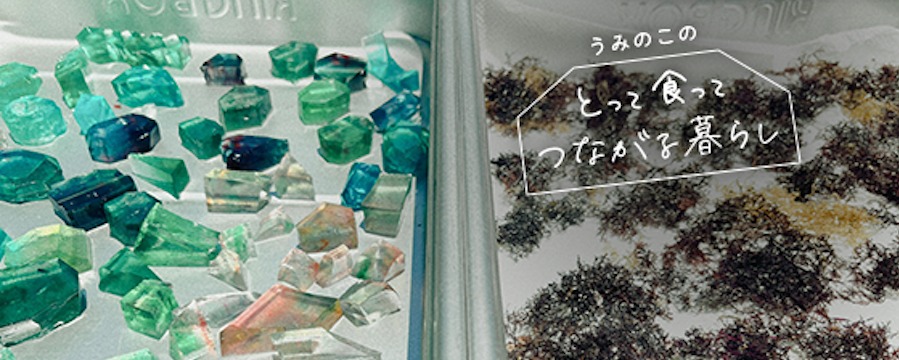パッシブラーニングも〜『エデュカーレ』2024年9月号より〜#04

今年度より、その一部をHoiClueにてご紹介しています。
今回お届けするのは、『エデュカーレ』2024年9月号より「パッシブラーニングもー「今日は風を感じに行こう」、そんな散歩があっても」です。
『エデュカーレ』
東京大学名誉教授の汐見稔幸先生が責任編集を務める、保育者と親のための学び&交流誌。
「保育のことをもっと勉強したい!」「悩みについてみんなの意見を聞きたい!」「自分の思いを発信したい!」そんな人たちのための雑誌です。
https://ikuji-hoiku.net/educare/index.html
『エデュカーレ』2024年9月号「Shiomi's eyes「保育のスピリット」」 第21回より
パッシブラーニングもー「今日は風を感じに行こう」
子ども主体の保育ということがいわれて、全国の園で子どもの自発的で積極的な遊びを生み出すことがテーマになっています。保育者が主導して子どもに何かをさせるというのでは、本当の意欲や能動的な心持ちが育たないことがわかってきたからです。そのキーワードがアクティブラーニングでした。
が、です。
少しあまのじゃくかもしれませんが、アクティブラーニングも大事だけど、それとは逆の学びも大事ということが忘れられていないか、と心配しています。
それは、もっとパッシブな学びを大事にしよう、ということです。
たとえば、晴れて雲がきれいに浮かんでいる日に、みんなでどこかに寝転がって雲を観察し、じっとそれが流れていくのを見ていよう、とか、外に出て鳥の声が聞こえるところに出かけたとき、子どもたちと「耳を澄ましてみよう」と、じっと聞こえるものを待ってみるとか、最近はあまりしないのではないでしょうか。
レイチェル・カーソンが「センス・オブ・ワンダー」の大事さを訴えたのは有名ですが、カーソンが訴えたこの世界に不思議さを感じる大事な感性は、紛れもなくパッシブな感性でした。
アクティブ、つまりこちらからどんどん働きかけ、そこから何かを学びとって脳に詰め込んでいくという学びではなく、感性を研ぎ澄まし、向こうから何かが届くのをじっくりと待つ、その先に生じる学び。こんな学びが今は衰えている気がしています。みなさんはそう思いませんか。
川の流れが聞こえたら「何て言って流れてるかな?」と聞いてみましよう。「ピコピコピコピコ、ポットンって言ってる」「ボソボソ、ツンツン、ポコピンって聞こえる」。耳を澄ませば、世界は詩に満ちています。「今日は風を感じに行こう」、そんな散歩があってもいいではありませんか。パッシブラーニングこそが、真に世界にアクティブになる手法なのです。
文:『エデュカーレ』編集長、白梅学園大学名誉学長 汐見稔幸
もっと知りたい方へ
今回ご紹介した記事は、 『エデュカーレ』2024年9月号に掲載されています。
【特集】
保育者のリアルな悩みに答えます 絵本についての6つの質問
エデュカーレ『保育のスピリット』
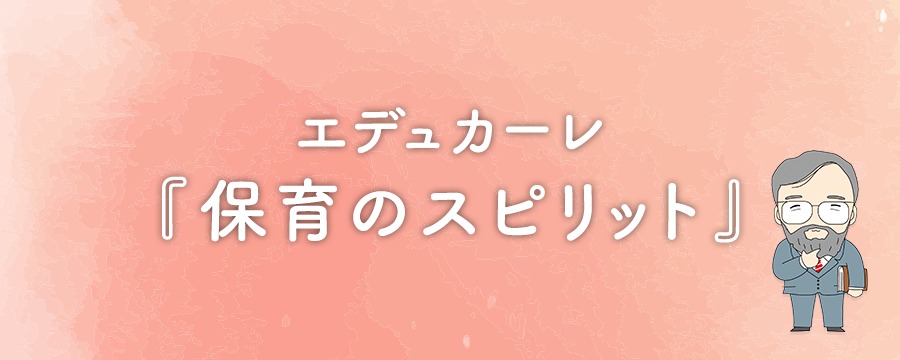
エデュカーレの汐見稔幸編集長の連載、「保育のスピリット」。2025年度より、その一部をHoiClueにてご紹介しています。
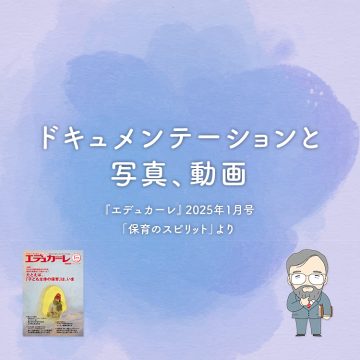
ドキュメンテーションと写真、動画〜『エデュカーレ』2025年1月号より〜#05
2026/01/29
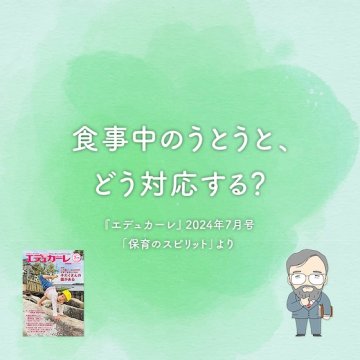
食事中のうとうと、どう対応する?〜『エデュカーレ』2024年7月号より〜#03
2025/09/25
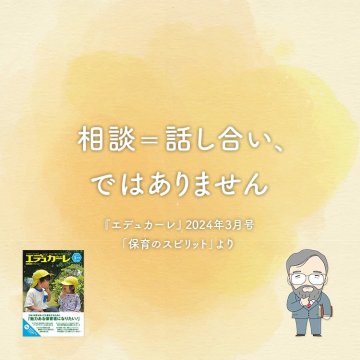
相談=話し合い、ではありません〜『エデュカーレ』2024年3月号より〜#02
2025/07/24

 エデュカーレ
エデュカーレ