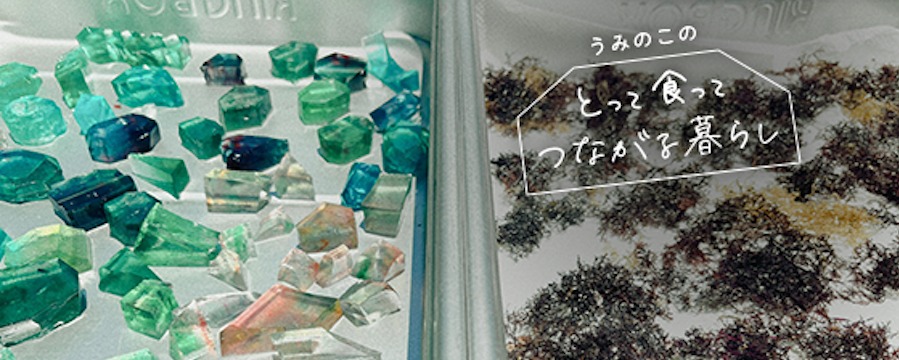「子ども主体」の保育をこう言いかえてみては?〜『エデュカーレ』2024年1月号より〜#01

今年度より、その一部をHoiClueにてご紹介していきます。
今回お届けするのは、『エデュカーレ』2024年1月号より「「子ども主体」の保育をこう言いかえてみては?」です。
『エデュカーレ』
東京大学名誉教授の汐見稔幸先生が責任編集を務める、保育者と親のための学び&交流誌。
「保育のことをもっと勉強したい!」「悩みについてみんなの意見を聞きたい!」「自分の思いを発信したい!」そんな人たちのための雑誌です。
https://ikuji-hoiku.net/educare/index.html
『エデュカーレ』2024年1月号「Shiomi's eyes「保育のスピリット」」 第18回より
「子ども主体」の保育をこう言いかえてみては?
「子ども主体の保育」ということの意味や、主体性という語の意味をめぐって、疑問や問いが絶えません。
多いのは、子どもに好きなことを好きなようにさせると、何でも好きなようにやればいいというわがままな子になるのでは?という趣旨のものと、子どもにこういう子に育ってほしいという保育者の願いは必要ないのですか?という趣旨のものです。
これはそれぞれもっともな意見であり、疑問だと思います。
保育は、戦後は保護教育を略して保育というのだと説明されていましたから、教育の一つであり、子どもを意識的に育てるという意図を持った営みです。ですからそこに保育者の願いは不可欠です。問題はその願いが、子どもも親も社会も納得のいく願いになっているかどうか、目指す子ども像、人間像のていねいな吟味が大事ということです。
OECDは、21世紀中盤を担う子どもたちに育てるべき人間性として、これまでキー・コンピテンシーという概念を提案してきました。日本では資質・能力と訳しています。今はそれを発展させたエージェンシーという概念で、目指す人間像を描いていますね。基本は、社会をよくするために行動できる力です。
日本でも、みんなでていねいに吟味して目指す子ども像や人間性を明らかにすべきと思いますが、そういう子どもへの期待は、保育の節々に保育者の要求として出てきます。やはり議論する力を身につけなければ、と思っていれば、保育の折々に、子どもたちに議論をすることを要請するでしょう。そこに保育士の願いが浮かび出てきます。
そうだとすると、子ども主体の、ということはできるだけ子どもの気持ちを大事にしつつ、保育者の願いと子どもの気持ちをていねいにより合わせて保育の実際をつくるということになるはずです。わかりやすく言うと、「できるだけ子どもの気持ちを大事にし、可能な限り子どもと相談して進める保育」ということです。
子どもの気持ちにできるだけ寄り添う、でもここはというときは子どもに提案して意見を聞き、相談して納得して決める、ことです。
<できるだけ子どもの気持ちを大事にし、可能な限り子どもと相談して進める保育>
これが子ども主体の保育の実際の意味なんです。
文:『エデュカーレ』編集長、白梅学園大学名誉学長 汐見稔幸
もっと知りたい方へ
今回ご紹介した記事は、 『エデュカーレ』2024年1月号に掲載されています。
【特集】
・残業が減らない、休憩が取れない…を解消するには?
・働き方改革、バリエ「二十二計」
エデュカーレ『保育のスピリット』
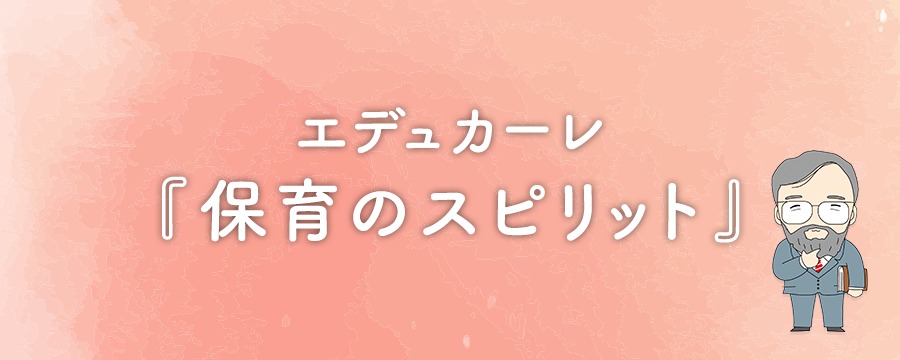
エデュカーレの汐見稔幸編集長の連載、「保育のスピリット」。2025年度より、その一部をHoiClueにてご紹介しています。
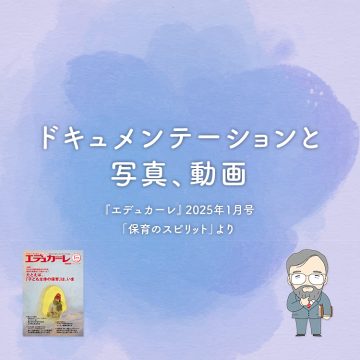
ドキュメンテーションと写真、動画〜『エデュカーレ』2025年1月号より〜#05
2026/01/29
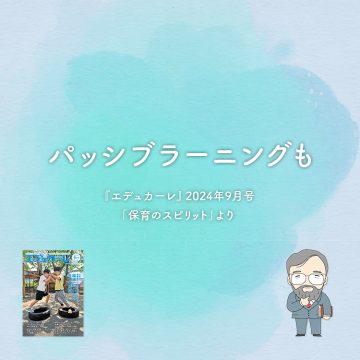
パッシブラーニングも〜『エデュカーレ』2024年9月号より〜#04
2025/11/27
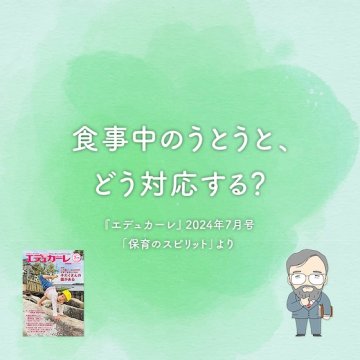
食事中のうとうと、どう対応する?〜『エデュカーレ』2024年7月号より〜#03
2025/09/25
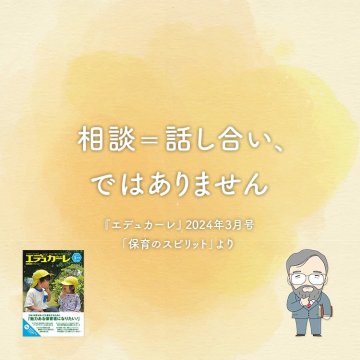
相談=話し合い、ではありません〜『エデュカーレ』2024年3月号より〜#02
2025/07/24

 エデュカーレ
エデュカーレ