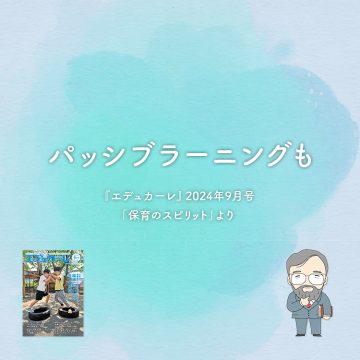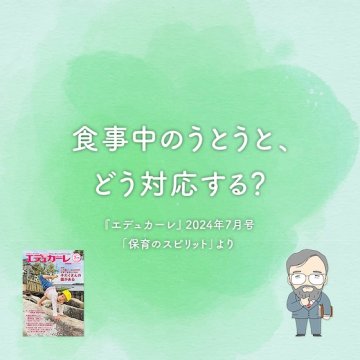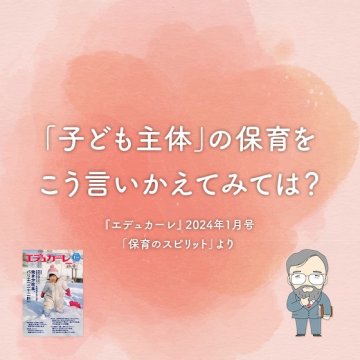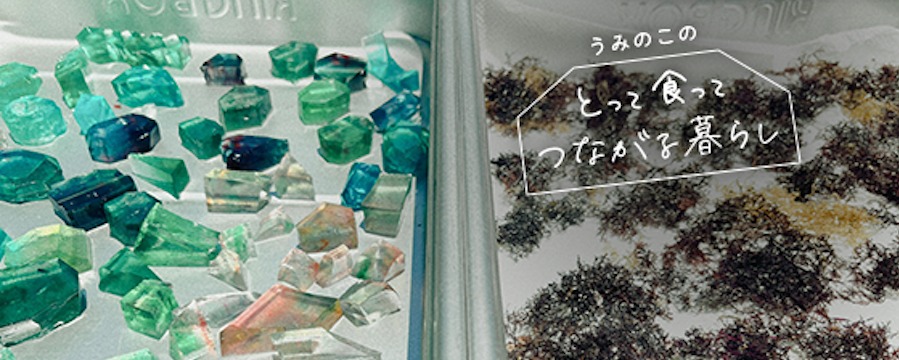相談=話し合い、ではありません〜『エデュカーレ』2024年3月号より〜#02

今年度より、その一部をHoiClueにてご紹介しています。
今回お届けするのは、『エデュカーレ』2024年3月号より「相談=話し合い、ではありません」です。
『エデュカーレ』
東京大学名誉教授の汐見稔幸先生が責任編集を務める、保育者と親のための学び&交流誌。
「保育のことをもっと勉強したい!」「悩みについてみんなの意見を聞きたい!」「自分の思いを発信したい!」そんな人たちのための雑誌です。
https://ikuji-hoiku.net/educare/index.html
『エデュカーレ』2024年3月号「Shiomi's eyes「保育のスピリット」 第19回より
相談=話し合い、ではありません
前号のこの欄(※こちらで紹介しています)、相談しながら進める保育ということを提唱したのですが、それに対する意見がネットに出ていました。「保育では子どもの話し合いで進めるのは、時間もかかるし難しい」という趣旨です。
私は、もしかすると相談=単なる子どもの話し合いと受け取られることがあるのかな、とちょっと驚くと同時に用語の提案の難しさを感じました。
前号で言いたかったのは、「子ども主体の保育」の名の下で、保育者が自分の願いを議論したり吟味したりすることがおろそかになっていないか、ということです。保育者の願いの内容とその願いに沿った資質・能力が育っているのかの吟味です。
実際の保育の場面では、今から何をしたいか、子どもに聞くことも、保育者が提案することもあるでしょう。そのとき子どもの反応が気分的で、意見(子どもの願い)がまとまらないこともしばしばあります。
さらに保育する側が、子どもの態度を見たり、意見を聞いたりして、推量し、再提案して、また意見を聞き、定まらないと思えば、ここはと思って強く提案することも多いでしょう。
そのような場合、子どもの意見や気分をよく観察してそれをアセスメントして、できるだけ子どもの気分を生かし、でもここは保育者が明確に提案しようとして進めているのではないでしょうか。まだ言葉の話せない0歳児の保育でも、そういう関わりをしていると思います。
大事なのは、保育者の願いと子どもの願いの接点で、子どもの願いをアセスメントしながら進めているかということです。そのプロセスを私は子どもと相談しながら、と表現しました。
少なくとも、子どもに任せて話し合いをさせ、子どもの意見を尊重しさえすればいいということではありません。大人が参加して、子どもと大人の願いの接点をさぐるアセスメントが私の考える「相談」です。
ときに、時間がかかることはあるでしょう。そうであっても、両者の願いの接点を、ていねいにつくっていくことを大切にしたいと思っています。
文:『エデュカーレ』編集長、白梅学園大学名誉学長 汐見稔幸
もっと知りたい方へ
今回ご紹介した記事は、 『エデュカーレ』2024年3月号に掲載されています。
【特集】
・自信を持って仕事をするために「魅力ある保育者になりたい!」
エデュカーレ『保育のスピリット』
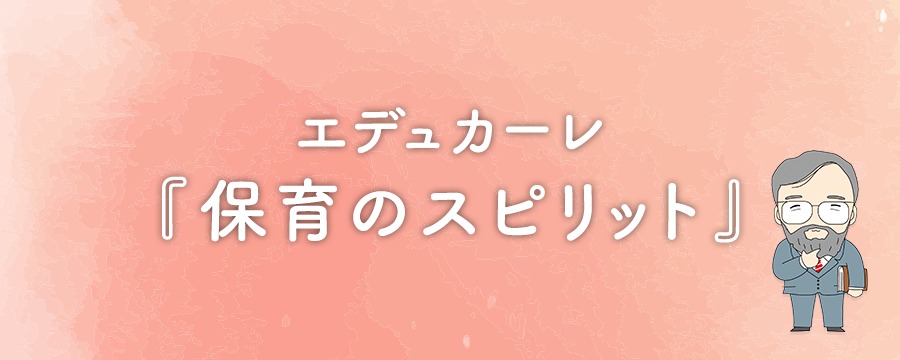
エデュカーレの汐見稔幸編集長の連載、「保育のスピリット」。2025年度より、その一部をHoiClueにてご紹介しています。

 エデュカーレ
エデュカーレ