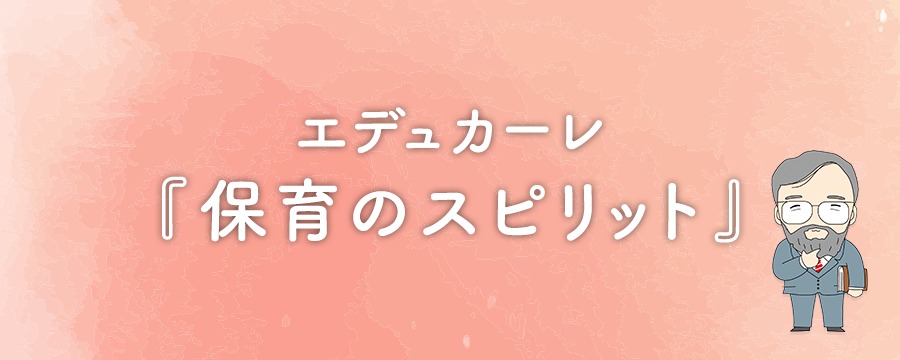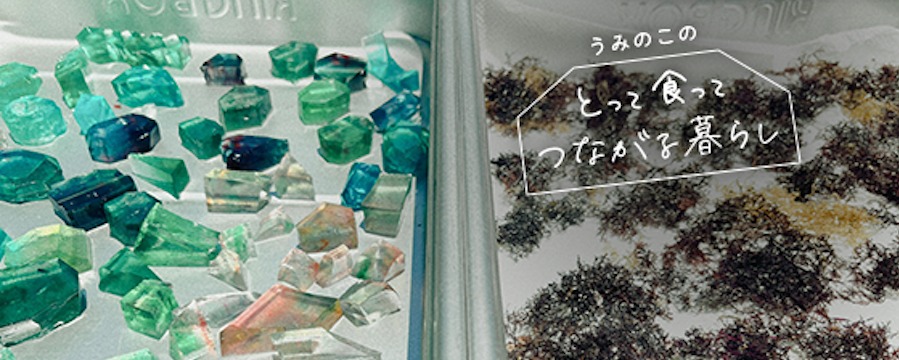防災は、関係づくりからはじまる ― 臨床心理士・桑野恵介さんに聞く、“もしも”に向けて今できること(後編)

前編では、発達に凸凹のある子どもとの避難訓練について、一人ひとりの状況に合わせたスモールステップでの支援やアセスメントの重要性など、具体的なお話をしてくださった、臨床心理の専門家で株式会社スペクトラムライフ代表取締役の桑野恵介さん。
後編では、実際に災害が起こり、子どもたちが安全な場所に避難した「その先」で求められる配慮や、日頃から大切にしたい関わりについて、さらにお話ししてくださいました。
桑野恵介 先生
株式会社スペクトラムライフ代表・臨床心理士・ 自閉症超早期療育法ESDM 認定セラピスト・入間市児童発達支援センター業務受託事業者・元 国立障害児施設心理療法士および療育指導室主任。
避難した後、も考えよう。
ここまでは、避難訓練での具体的な配慮についてお話をさせてもらいましたが、実は、災害が起きて避難した後のこともしっかり考えておくことが必要です。
ー 避難の後のこと、ですか。どういうことか教えてください。
大きな災害の場合、保護者の方が迎えに来られるまでに、かなりの時間がかかることも想定されます。東日本大震災の時には、園で深夜まで子どもを預かっていたというケースも少なくありませんでした。ですから、避難した後も、ある程度の時間を安心して過ごせるような準備と配慮がとても大切になります。
ー 避難場所に移動して、とりあえず安全は確保できた、では終わらないのですね。具体的に、どのようなことを考えられているといいのでしょうか?
まず、トイレの問題です。断水などで園のトイレが使えなくなることもありますので、発達に凸凹がある子は特に、おむつや簡易トイレは少し多めに用意すると良いと思います。また、その時に、発達に凸凹がある子の中には「いつもと違う」ということが非常に苦手という子もいるので、どんなものなら使えるのかといったようなことを、事前に保護者の方に確認しておくことも重要ですね。
食事についても同様で、偏食のある子も少なくないので、一般的な備蓄食では食べられない可能性も考えて、その子が食べられるもの、飲めるものを事前に確認し、必要であれば保護者の方にご準備いただいて預かっておくといったこともしておくといいと思います。
もし、その子が医療機関や療育機関に通っているのであれば、保護者の方だけでなく、医師や療育の担当者にも情報を求めて、可能な範囲で備えておくことが大切です。
それから、意外と見落としがちなのが「暇つぶし」。何時間も待つ間、何もすることがないと不安が増してパニックにつながってしまう子もいます。その子が好きで落ち着けるような暇つぶしグッズを準備しておけるといいですね。
ー 暇つぶし、ですか。どうしても「逃げる」ことばかりに意識がいってしまって、その後の過ごし方まであまり考えが及びませんでした。確かに、見通しが立たない状況で長時間過ごすのは大人でも辛いですから、子どもたちにとってはなおさらですね。
おっしゃる通りです。「ママやパパはいつ来るの?」という不安は、発達に凸凹のある子、特に自閉症スペクトラムの子にとっては非常に大きなストレスとなり、そこから不安定になってしまうこともあります。どんな暇つぶしグッズだと安心できるのか、集中できるのか、どんなものが有効かは個別性がとても高いので、事前に保護者や連携機関の方と相談しておくといいと思います。特殊なものであればご準備いただいて預かっておく。そして、いざという時にそれも持って避難できるようにしておくと安心です。
あと、一目で配慮が必要だとわかるような、いわゆる障害者マーク(赤地に白十字のヘルプマークなど)を災害時につけておくと、一般の方々が多くいる避難所に移動した際などに、声をあげてしまったり騒いでしまったりしても、周囲の理解を得やすくなる可能性もありますね。
ー こうした一人ひとりに合わせた細やかな準備を考えると、やはり「個別避難計画」も合わせて用意することが、子どもの命を守ることにつながっていくんだと、お話を伺いながら感じました。
個別に合わせた配慮を考えるのが大変そう、自分に準備することができるだろうかと不安に思われる保育者の方もいらっしゃるかもしれないですが、有益なサイトも色々ありますから参考にしてみるといいと思います。
いくつか紹介しますと、一つ目は、「国立障害者リハビリテーションセンター」のサイト。私の元の職場なんですけど、厚生労働省と子ども家庭庁の管轄の機関なので、国のオフィシャルな情報が集まっているので、信頼性の高いサイトになると思います。
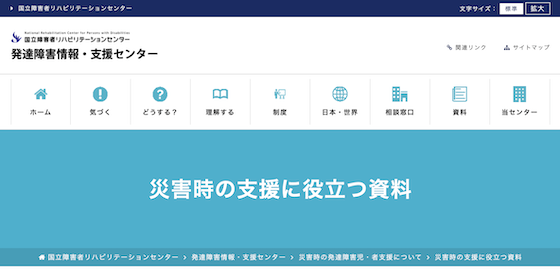
▶ 災害時の支援に役立つ資料(国立障害者リハビリテーションセンター)
あとは、「国立特別支援教育総合研究所」が運営する、特別支援教育に関しての研究や情報が集まっているサイト。特別な支援が必要な子どもとその家族のための緊急時対応準備マニュアルや、学校における子どもの心のケアサインを見直さないための災害時の支援ハンドブックなど、色々載っています。
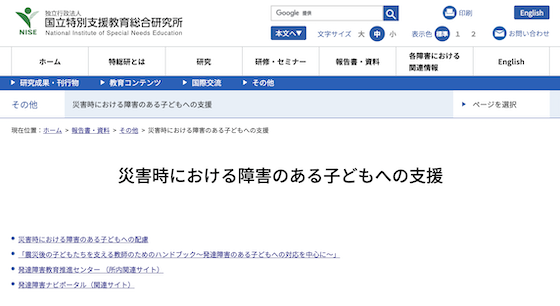
▶災害時における障害のある子どもへの支援(国立特別支援教育総合研究所)
それから、「ファミケア」というサイトもおすすめです。障害のあるお子さんを持つご家庭での工夫や必要な情報を集めているサイトで、発達障害児の防災というテーマで記事が書かれていたり、実際に保護者の方の被災経験談が紹介されていたりして、実用的な情報が得られると思います。

▶障がい児の防災対策(疾患や障がいのある子を育てる家族のための情報サイトファミケア)
また、「発達障害感覚グッズ」などのワードでインターネット検索してみるのもいいと思います。先ほどお話ししたイヤーマフや、感覚的に暇つぶしができるようなグッズが購入できるサイトや情報が手軽に見つかることもあります。
何よりも大切なのは、日頃からの「信頼関係」
ここまで、避難訓練から実際の災害時の対応まで色々なお話しをさせていただいてきましたが、何より大切なのは、日々の子どもたちとの信頼関係づくりだと思います。
ー 日頃の信頼関係づくりが大事。
そうです。というのも、東日本大震災を経験された方の話を聞いたり、私自身が支援をしたりしていて感じるのは、大人との信頼関係がしっかりできている子の場合、普段はなかなか言うことを聞いてくれないような子でも、「今は非常事態なんだ」「先生たちは真剣なんだ」ということを察して、いつもよりずっと指示が通りやすくなるケースがあるんですよ。
その子がどう感じているのか、何がしたいのか、何が分かって何が分からないのか、といったことに、日頃から気を配っておくこと。災害が起きたから特別なことをするのではなく、日頃から子どもたちの内面に目を向け、思いを寄せていること。それが、いざという時に子どもたちが保育者を信じて、落ち着いて行動してくれることにつながり、緊急時に子どもとコミュニケーションを取りながら避難したり、一緒に時間を過ごしたりすることを可能にするのだと思います。
繰り返しになりますが、日頃の子どもたちとの信頼関係づくりが、緊急時に本当に力を発揮します。日々、子どもたちのために心を砕いておられる保育者の方々の努力は、必ずそういった場面で実を結びます。子どもたちはきっと先生たちを信頼してくれますから、ぜひ子どもたちを信じて、安心して避難訓練に取り組み、いざという時に起こりうることを想像しておいていただければと思います。
前編はこちら
臨床心理士・桑野恵介さんと考える、発達に凸凹がある子どもとの「避難訓練」。(前編)
読者の皆さんの中にも、一人ひとりに合った対応が大切と分かっていても、具体的にどのような準備や配慮をすれば良いのか迷い、日々試行錯誤されている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回、臨床心理の専門家であり、株式会社スペクトラムライフ代表取締役の桑野恵介さんに、発達に凸凹がある子どもたちとの避難訓練のポイントについて、お話を伺いました。
災害から、子どもを守る。
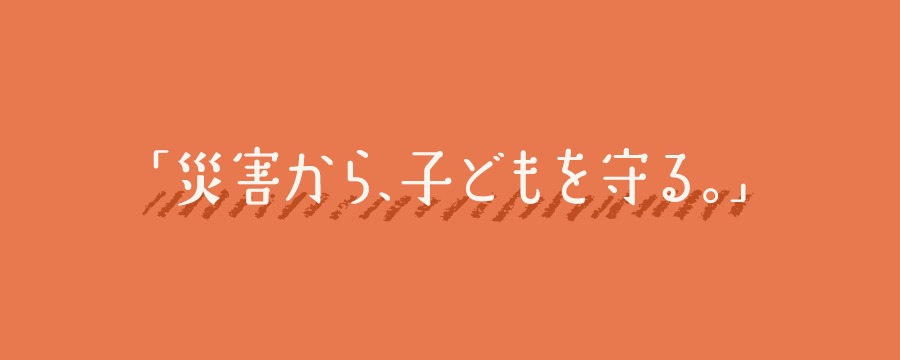
「もしも」の時、子どもたちを守るために私たちができることは何か。備えについて、日頃の工夫や取り組みについて、“もしも”のその先のことについて。さまざまな観点から『災害から、子どもを守る』ということについて考えていく企画です。
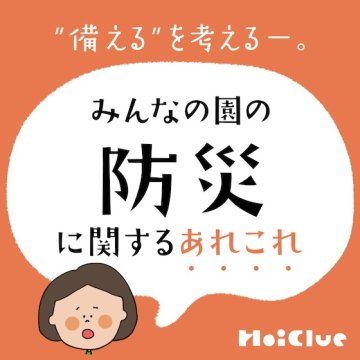
【アンケート結果】“備える”を考えるー。みんなの園の「防災」に関するあれこれ
2025/10/01
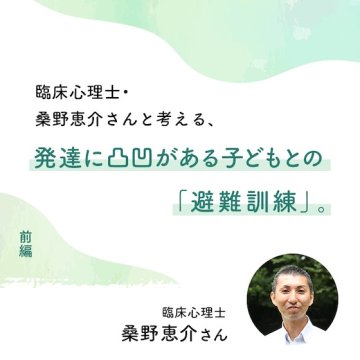
臨床心理士・桑野恵介さんと考える、発達に凸凹がある子どもとの「避難訓練」。(前編)
2025/07/18

子どもの心のケアなどに関する情報リンク集(災害などの緊急下に寄せて)
2024/01/06

 三輪ひかり
三輪ひかり