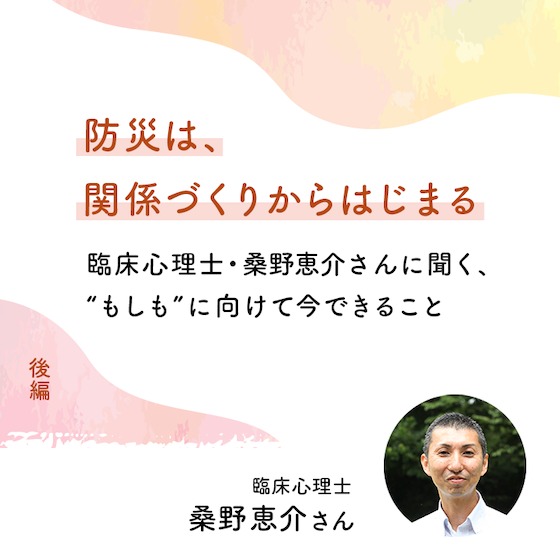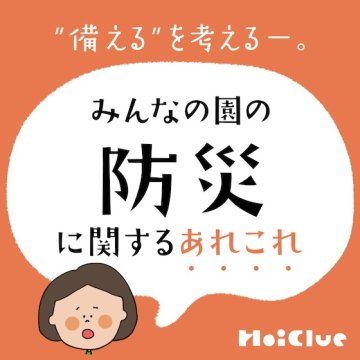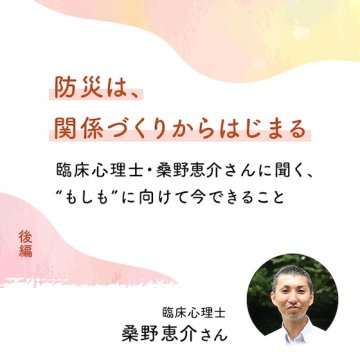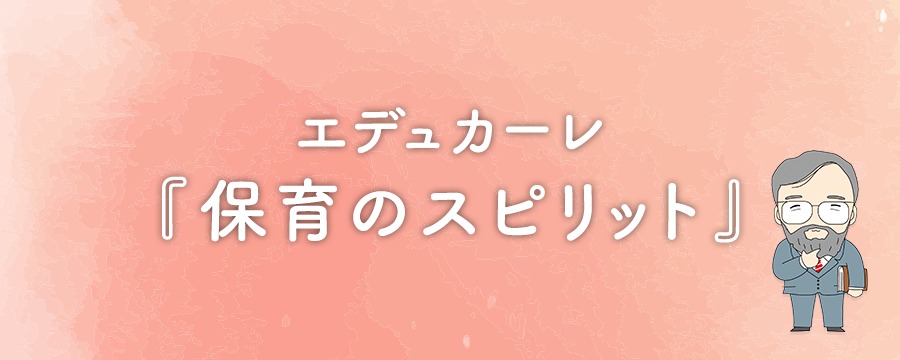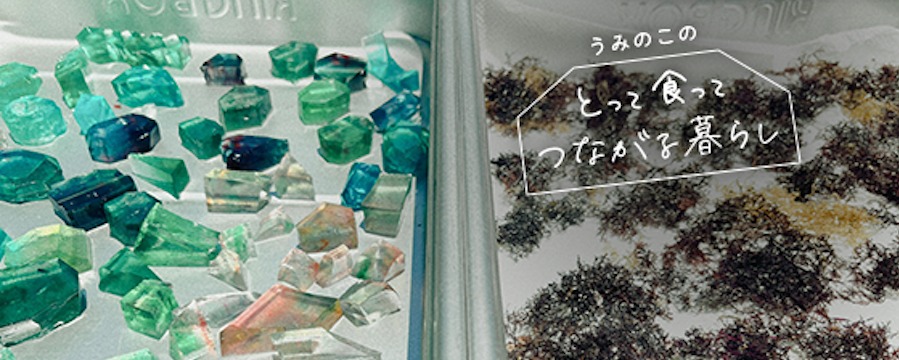臨床心理士・桑野恵介さんと考える、発達に凸凹がある子どもとの「避難訓練」。(前編)

読者の皆さんの中にも、一人ひとりに合った対応が大切と分かっていても、具体的にどのような準備や配慮をすれば良いのか迷い、日々試行錯誤されている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回、臨床心理の専門家であり、株式会社スペクトラムライフ代表取締役の桑野恵介さんに、発達に凸凹がある子どもたちとの避難訓練のポイントについて、お話を伺いました。
桑野恵介 先生
株式会社スペクトラムライフ代表・臨床心理士・ 自閉症超早期療育法ESDM 認定セラピスト・入間市児童発達支援センター業務受託事業者・元 国立障害児施設心理療法士および療育指導室主任。
命を守るための避難訓練。
ー まず最初に伺いたいと思っていたのは、避難訓練への参加の可否です。そもそも、発達に凸凹がある子どもたちも必ず訓練には参加をした方が良いのでしょうか?
避難訓練への参加の可否についてですが、基本的には参加をしてもらった方がいいです。
パニックを起こしてしまうから参加させない方がいいのでは、と思われる保育者の方もいるかもしれませんが、災害は本当に起こる可能性があることです。その時にどんな問題が起こり得るのかを想定できていること、またそれに合わせて繰り返し訓練ができているということが、子どもの命を守ることにつながります。子どもだけではなく、保育者の先生方の練習としても避難訓練は大切な場ですね。
ただ、子どもに無理をさせてくださいということではありません。例えば、入園したばかりであるとか、年度が変わったばかりであるというような状況で、明らかにその子がナーバスになっていて、毎日パニックを起こしていたり、ものすごく不安定な状態の場合には、「今回は避難訓練の参加を見送ろう」という判断も必要です。凸凹のある子どもたちの中には、一度状態を大きく崩してしまうと、そこからなかなか状態を戻しづらいということもありますから。それこそ、そんな状態の時に本番が来たら余計避難ができなくなるという可能性も考えられます。ですので、ケースバイケースで、子どもの様子をしっかり観察しながら現場で判断してみてほしいなと思います。
ー 子どもの姿にしっかりと目を向けながらも、命を守ることが最優先のため、基本的には訓練には参加をするということですね。訓練への参加の方法についてもお聞きしたいのですが、どのように一人ひとりの子どもにあった支援を考え、避難訓練を実施していくべきでしょうか?
避難訓練のあり方や実際の避難の仕方は、特に発達に凸凹があったり、障害がある子どもたちに対しては、非常に個別性が高いです。その子に合わせたスモールステップで支援していく必要があります。
もし、新しく担任になったなどでまだその子の訓練での様子がわからない場合には、一度は何の支援や配慮がない状態で避難訓練へ参加するのがおすすめです。そこで、アセスメントをして、どんな問題が起こるのかを確認した上で次の避難訓練からはその子にあった配慮をしていく。そして、回数を重ねていくうちに徐々に、実際の災害本番に近い形に近づけていくという段階をふむといいかなと思います。
避難できるためには、何が必要か考える。
ー まずは何も支援のない状態でアセスメントをとるとのことでしたが、そのアセスメント(客観的な視点で観察する)では、どういう視点を持つことが大切なのでしょうか。
避難できるかどうか、という一点です。そこに支障がある場合に、何が避難を困難にしているのかを把握し、どんな支援が必要なのかを考えていきます。
というのも、平時と緊急時は分けて考えるべきだと私は思っています。普段の保育の中では、子どもたちの発達や心のケアにまず目を向けますよね。それこそ、言うことを聞いてくれていたとしても見通しが持てていないとか、行動的には落ち着いていても強い不安を感じているとか、そういった目に見えない部分まで考えて支援をする。でも、緊急時で命の危険があるとなった時には、やはり命を守るということが第一になりますから、「避難ができるかどうか」ということを一番に考えるべきです。
ー スモールステップでの支援について、もう少し具体的に教えていただけますか?例えば、感覚過敏のある子どもには、どのような配慮ができるでしょうか。
例えば、聴覚過敏でサイレンの音にパニックを起こしちゃう子なら、そのサイレンがどこから鳴るのか、鳴ったらどうするのかということを事前に予告をしておくといいでしょう。それでも難しいようであれば、まずはサイレンなしで行動だけの練習をして、その後「サイレンが鳴るよ」と予告をして訓練をする。それから、本番と同じ設定で予告もなしでサイレン、というように、やはり、スモールステップでやっていくことがいいと思います。
他にも、イヤーマフを準備しておくのも有効ですね。避難の時のサイレンだけでなく、地震の時には緊急地震速報も鳴ります。音が大きいですし、普段聞いたことないような音なので、子どもたちも驚いてしまう可能性がありますから。
それこそ、避難場所に一時避難した後も緊急地震速報は繰り返し鳴る可能性もありますので、避難した後は例えば携帯の音が鳴らないようにするとか、音が聞こえづらいような場所にしまっておくとか、そういうこともできるかと思います。
個別避難計画で、一人の子をみんなで見守る。
ー 本当に一人ひとりできる対策が違うのですね。アセスメントとスモールステップで訓練を進めていく以外にも、何かできることがあれば教えてください。
園全体でどう行動するのか、どんな準備をしておくのかという避難計画や業務継続計画というものを作成していると思いますが、それとは別に「個別避難計画」の作成が有効だと思います。
個別避難計画があれば、いざとなった時に、クラスの担任以外でも対応が可能になりますし、担任が変わる年度替わりの時などでもその子に合わせた配慮を継続できるようになります。
ー 個別避難計画にはどんなことが載っているといいのでしょうか?
パニックの引き金になるものが特定できている場合や、キーパーソンが決まっている場合には、そのことは載せておくといいですね。他にも、心を落ち着かせたり、時間を潰すのに有効な物や関わり方があれば重要な事項としてまとめておく必要があると思います。
ー 担任ではない人もみる可能性があると考えた時、個別避難計画を作る上で分かりやすさも大切になってきそうだと、お話しを聞きながら感じました。
その通りですね。たくさん情報を書いてしまうと、いざとなった時に読みづらい、重要な事項は何なのか分かりづらいということもあるかと思うので、本当に大事なものだけを箇条書きで書いておくくらいがちょうどいいかもしれません。
現場で使いやすい形にしておくこと、本当に必要な情報はなんだろうということをしっかりと考えることがとても大切だと思います。
後編はこちら
防災は、関係づくりからはじまる ― 臨床心理士・桑野恵介さんに聞く、“もしも”に向けて今できること(後編)
後編では、実際に災害が起こり、子どもたちが安全な場所に避難した「その先」で求められる配慮や、日頃から大切にしたい関わりについて、さらにお話ししてくださいました。
災害から、子どもを守る。
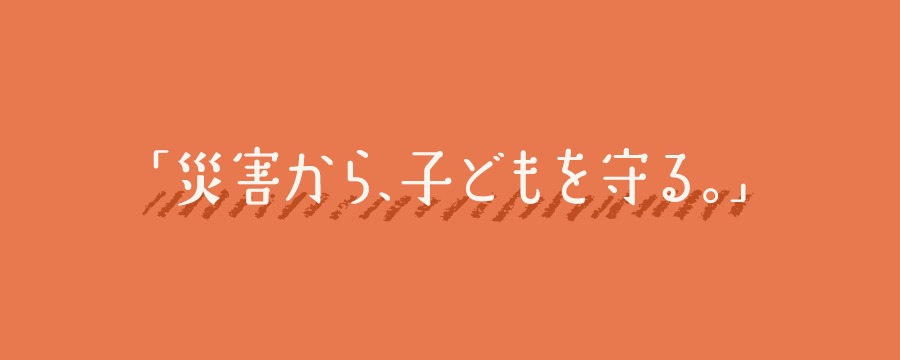
「もしも」の時、子どもたちを守るために私たちができることは何か。備えについて、日頃の工夫や取り組みについて、“もしも”のその先のことについて。さまざまな観点から『災害から、子どもを守る』ということについて考えていく企画です。

 三輪ひかり
三輪ひかり