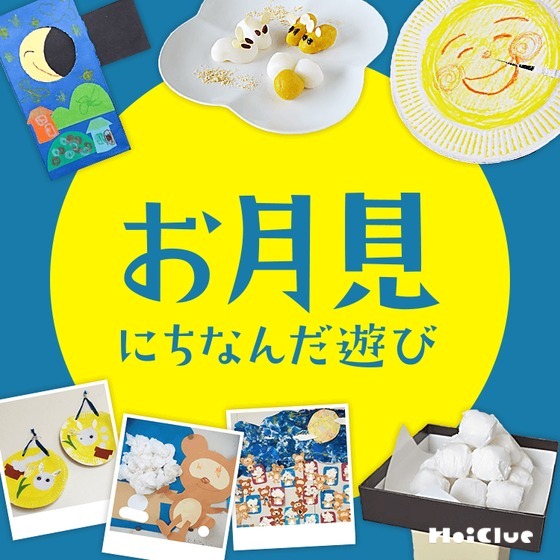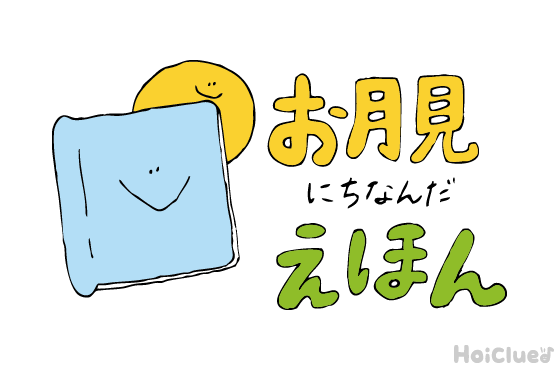【2026年版】十五夜(9月25日)とは?〜子どもに伝えやすい意味や由来、過ごし方アイデア〜

お月見とは…?
どうしてお団子を食べるの?本当に月にうさぎはいるの?
“十三夜”もあるって本当?
子どもに伝えやすい十五夜やお月見、過ごし方アイデアをご紹介します。
十五夜ってなぁに?(旧暦8月15日)
十五夜は、一年のなかで一番きれいなまんまるの満月が見える日のこと。
毎年、日にちが変わります。
2026年の十五夜は、9月25日です。
お月見とは?
日本では、お団子やお餅、ススキや里芋などをお供えして、お月様を眺めることを「お月見」といいます。
ちなみに「お供え」というのは、神様に捧げること。
「神様もどうぞお食べになってくださいね」というような意味です。
もともとお月見は、「中国」という国がしていて、8月15日は里芋がたくさん取れる時期だったそう。
たくさんのおいしい食べものが食べられることへの「ありがとう」の気持ちと、これからもおいしい食べ物が食べられますように…という「願い」を込めてお供えするお月見が、日本にも伝えられました。
どうしてススキやお団子をお供えするの?
十五夜の季節…秋にはおいしい食べ物がたくさん収穫されるよね。
「おいしい食べ物があるから幸せだ!みんなで分けあおう」という意味がこめられているんだって。
過ごし方アイデア
十五夜(9月25日)には、どんな過ごし方があるでしょう…?
月を見上げて、想像してみる
月をよーくみてみると…
何か見えるかな?何が見えるだろう?
日本から眺めた月は、「ウサギが餅つきをしているように見える」と言われています。
大きなカニや、女の人の横顔にみえる国もあるのだそう。
いろんな表情のある月を子どもたちが見たら、どのように見えるでしょう…?
お月見の日や、その翌日に子どもたちと話をしてみるのも楽しそうです。
行事を通して、子どもたちと遊んでみる
十五夜という行事を通して、子どもたちと一緒にお団子を作ってみたり、いつもの散歩コースに生えているススキを飾ってみたり、大きな月を作って教室に飾ってみたり…
ということで、十五夜に楽しめそうな遊びをいくつかピックアップしてご紹介します!
お月見にちなんだ遊び〜十五夜の時期に楽しめそうな遊びアイデア集〜
十五夜時期に楽しめそうな遊びや、お月見のお供に欠かせないお月見団子など、お月見にちなんだ遊びアイデアをまとめてみました。
お月さまやお月見にちなんだ絵本&絵本あそび6選
そんなお月さまが身近に感じられる絵本から、お月見にちなんだ絵本まで盛りだくさん!
クルクル回るお月さまに、お月さまパズルまで…お月さまにちなんだ発展遊びもご紹介!
おまけ
十三夜(旧暦9月13日)
十五夜とは別に、“十三夜”という言葉を聞いたことはありますか?
十三夜のお月様は、左側が少し欠けています。十五夜と同じように、毎年日にちが変わります。
2026年の十三夜は、10月23日です。
十五夜と十三夜の違いは…?
十三夜は、日本だけの行事なのだそう。
「十五夜に、お団子を食べて月見を楽しむのなら、十三夜にも同じ場所でも月見をしよう」ということで、日本では十三夜にもお月見をしているんだって。
十五夜だけを楽しむのを「片月見」といい、「十三夜を月見しないことによって、災いがやってくる」とも言われているのだとか。
だから日本では、【十五夜】と【十三夜】っていうお月見の日があるのですね。
9月〜11月の行事
子どもたちに伝えやすい、秋(9月、10月、11月)の行事の由来や過ごし方アイデアの記事一覧は、こちらです。
▶9月〜11月の行事にちなんだ記事一覧

 ほいくる編集部
ほいくる編集部