行事を通して育つ子どもたちの姿〜HoiClue Lab.あそび探究室セッションレポート#06〜

HoiClueで運営している「HoiClue Lab.あそび探究室」。 Labメンバーさんとのセッションの時間が、毎回発見や気付きにつながることばかりなので・・・3期目となる今年度より、その中身を月1回、みなさんにもほんの一部だけお届けしていきたいと思います。
今回紹介するのは、2025年10月のセッションより「行事を通して育つ子どもたちの姿。どんなことを大切にしている?」をテーマに出てきた問いや話を、いつもと少し違う形でお届けします。



あそび探究室のLabメンバー
保育園、こども園、幼稚園、発達支援施設、児童館、園の外部講師など、さまざまな場で子どもたちと関わっているLabメンバー。経験年数やバックグラウンド、お住まいの地域も全国各地それぞれです。
今年度は11名で活動しています。
その日で終わりにするのは、もったいない!運動会にまつわる話
運動会当日が終われば次の行事へ…それで良いんだっけ?
運動会は、終わったあとの方が盛り上がる。
下の子たちが上の子たちの真似をして、そのまま発表会に繋がっていったことも。


行事に追われた保育をするのが嫌で小規模を選んだ。
普段行ってる公園で走ったり、遊んだりしている子どもの姿を見て、運動会ではかけっこや玉入れをやってみた。“今日で最後だから頑張ろう”というのではなく、運動会をきっかけに、子どもたちの遊びがまた続いていく。
運動会が終わっても続いたリレーごっこで、遅い子が省かれそうになったことがあった。子どもたちと話し合いをすると、『オレがこいつの分も走るから入れてやって』という子が。遊びが続いたからこそ見える子どもの姿に出会い、運動会の経験をそこだけで終わらせるのはもったいない、保育って柔軟なんだ、ということを子どもたちに教えてもらった気がする。


コロナをきっかけに行事を見直した。
子どもの主体性を考えると、子どもたちがやりたいことをチョイスしてやっていく流れになった。親子運動会の形にして、保護者は出ずっぱり!今年は、系列園の保護者対抗の競技など、親子同士の交流を深められたら・・・と考え中!
心が動いたものが表に出るのが表現。作品展にまつわる話
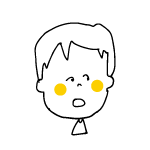
子どもが“やりたい”という気持ちで作ったものには、やっぱり心の動きが表現されている。心が動くというのが一番大事で、子どもの心をそっとつつくような大人の配慮が大切なのではないか。
「作品展」を「遊び展」という名前に変えた。
これといった決まりごとはなく、“どんなことをしてもいい”という印象を感じてもらうため、遊びの様子を動画で撮り貯めて編集し発表したり、おもちゃを置いておき親子で自由に遊んでもらったり、親子で作品に付け足して一つのものに仕上げてもらったりと展示の仕方も工夫している。


「〇〇を描く」とすると、描かなくちゃいけないと思ってしまう。でも「〇〇と出会う」などにすると、急に印象が変わると思う。
「表現」というのは、その子ども自身が、何かを作るためや描くためではなく、そのままの自分を表出している感じがする。

行事を通して見えてくるもの

自分の経験に加え保護者それぞれの声を聞くことが増え、行事は子どものため?保護者のため?など心が揺れ、いろいろな思いが出てきた。
自由が苦手な子にとっては、ある程度決まっていることに取り組むことで楽しめる子がいることも思うと何が正解かは複雑に感じる。でも、やっぱり子どもの姿を大切にすると、光る子どもの姿や喜ぶ保護者を見ることができるのだと思う。
子どもの“楽しさ”への入口はいろんな方向からでいいのかもしれない。
正解が一つじゃないから、保育はやめられない魅力がある。


行事はあってもいいし、なくてもいいのかもしれない。
行事があるとしたら、子どもたちとどう楽しむか、園全体としてどう考えるかなど、それは永遠のテーマかも。でも、子どもの姿を一人も取りこぼさないように毎日を過ごしていきたいと思うし、今度やる運動会がそういうものでありたいと思う。
***
保育の現場にいると、一年の中でいろいろな行事があるのではと思います。
今回のLab.は、行事が良いか悪いかということではなく、子どもたちの暮らしやあそびは、行事で途切れず、つながって続いていくものだということを改めて感じられる時間でした。
みなさんが行事を通して大切にしていることや、印象に残っている子どもたちの姿は・・・?
ぜひ読者のみなさんからも、「行事を通して育つ子どもたちの姿」など、今回のテーマにまつわるエピソードをお寄せいただけたらうれしいです。
それでは、次回のあそび探究室レポートをおたのしみに・・・!

 水岡香
水岡香